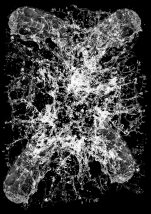- ホーム /
- チームパフォーマンスコーチ
当たり前のように
私達は、
毎日24時間という一日を
過ごしていますが、
私はよく思うのです、
凄いなぁ、と。
何が凄いかと言うと、
自然の摂理
がです。
自然の摂理と言うと、
なんか大袈裟ですが、
でも、
凄いと思いません?
必ず24時間サイクルで
一日が終わり、
一日が
始まるのですよ。
どれだけ心の中が
荒れようが、
どれだけ悩もうが、
どれだけ叫ぼうが、
時間は同じスピードで
進み、
しかも必ず
「次の日」
が来るのですよ。
これって
凄いことだと思いません?
この世は
様々な「循環」「サイクル」が
成り立っています。
その上で
私達は生きています。
「循環」「サイクル」という
存在そのものが
私は凄いと
思います。
地球は太陽の周りを
回り続け、
一日は24時間周期で
延々と続いていく。
継続していく。
循環があるからこそ
継続があり、
循環があるからこそ
進化がある。
凄いなぁ。
誰がこんなものを
創り上げたんだろう、
と
よく私は一人で
感心しています。
循環の中においては、
どこを
スタート地点にし、
どこを
エンド地点にするか?
はその人その人の
自由です。
でも、
必ず「節目」は
あります。
「節目」があるからこそ、
私達は何度も
「再スタート」が
できます。
循環がなければ
このようなことは
できません。
ホントに凄いなぁ、と
思いますね。
・・・・・・
人生というのは、
「一日」と「一日」の
コラボです。
よく、
一日一日の積み重なりが
人生である
という見方もありますが、
実は私は
ちょっと違った見方を
しています。
以前にもこのブログで
書かせていただいたことが
ありますが、
この3次元の世界は
すべてが「分離」しています。
昨日の自分と
今日の自分と
明日の自分は
すべてつながっているように
見えますが、
実は、それぞれが
別個の存在です。
時間の流れの中に
生きるということは、
それぞれの時間における
別個の自分を
時系列に沿って
一つ一つ順番に体験している、
ということなのです、
わかりづらいかも
しれませんが。
つまり端的に言えば、
昨日の自分は
昨日の自分でしか
ありません。
今日の自分は
今日の自分という
一つの存在です。
明日の自分は
明日の自分という
独立したものです。
人生とは、
そういった時系列に沿った
別個の自分達の
コラボなのです。
昨日の自分と
今日の自分と
明日の自分の
コラボです。
大事なのは、
それぞれの自分達が
良いコラボを
することです。
それぞれの自分が
反発をし合って
エネルギーを
打ち消し合っている、
という
そんなことをしている人も
残念ながら多いのですが、
それは実に
もったいない話です。
一日一日の
コラボ。
そして、
一日一日の
統合。
さらに、
一日一日の
融合。
そんなことができれば、
人生の展開は
すさまじく加速します。
つまり、
人生とは
単なる一日一日の
積み重なりでは
ありません。
一日一日の
相乗効果を起こすことこそ
人生の醍醐味であり
面白さです。
・・・・・・
そのためのコツは
「昨日はこうだったから
今日はこうするしかない」
・・・からの
解放です。
昨日の自分によって
今日の自分を
縛らない、ということです。
昨日は昨日。
そして、
今日は今日。
毎日を
ゼロ出発させます。
ゼロ発想を
します。
そんなことをすると
ちゃらんぽらんな
毎日になるのでは?
と思う人も
いるかもしれません。
でも
まったく逆です。
きちんと
「ゼロ」から発想すれば、
「ゼロ」は「ゼロ」のままですから、
つまりは、
その人の「原点」ですから、
「原点」は変わりませんから、
「ゼロ」に戻れば戻るほど、
その人には
「一貫性」が生まれるのです。
そして、
昨日の自分と
今日の自分の
融合が自然に起こり、
かつ、
相乗効果が起こるのです。
昨日のあの事柄が、
まさかこんな展開になるとは!
という驚きと喜び、
想定外の感動、
そんなものが
頻発するように
なるのです。
私の言う
『真本音』とは、
その
「ゼロ(原点)からの意志(意思)」
とも言えるでしょう。
自らの真本音を知り、
自らの真本音に素直に
行動することで、
一日一日の自分のコラボが
次々に
成されて行くのです。
楽しいですねぇ。
昨日に縛られた今日。
・・・これは不自由です。
昨日に縛られない今日。
・・・そんな日々は
自由です。
真本音に生きる人は
自由なのです。
つづく
後悔とは
痛みです。
本当に深い後悔は、
私達の心に
深い痛みを刻むだけでなく、
ある意味、
本当に傷を残します。
心だけでなく、
魂にも傷を残すことが
あります。
その傷は
何かの拍子に
すぐに疼きます。
その疼きに耐えられず、
痛みから逃れるように
私達は次の自分の行動を
決定してしまいます。
痛みから逃げるための
行動。
それは反応本音レベルの
行動となります。
反応本音レベルの行動は
周りの人の反応本音を
喚起します。
反応と反応の
関わり。
反応と反応の
コミュニケーション。
反応と反応の
絡み合い。
それらの多くは、
ぶつかり合いや
混乱や
さらなる強い反応を
呼び起こします。
そしてそれらの多くは
「エンティティ」と
なります。
「エンティティ」
つまりは、念の塊。
日本語に訳すと
「生き霊」。
それが職場であれば、
エンティティの
溜まり場が職場
という最悪の状態になります。
それがどのような現実を
引き起こすかは
想像に難くありません。
たとえ、
最初はほんの小さな
後悔の念だったとしても、
それらが積もりに積もって
そのような状態にまで
至ることも
決して少なくはありません。
・・・・・・
後悔をしない生き方を
するためには、
何か「大きく後悔するような出来事」
を引き起こさないように
すればよい、
というものではありません。
そういった大きな出来事は
小さな一歩一歩の
積み重ねの結果として
「必然的に」
起こるからです。
小さな一歩一歩の
出し方を変える、
つまりは
「生き方」を
変えるしかありません。
例えば、
小さな嘘やごまかしを
すぐにしてしまう人。
その一つ一つは
小さな後悔しか
生みません。
しかしその後悔の念が
溜まることで
念は大きくなり、
心や魂に傷がつきます。
そしてある時に
必然的に
大きな出来事が起こり、
その傷が決定的に
なります。
たまたま起きる
出来事は
一つもありません。
すべては
「生き方」の結果です。
一歩一歩の
「生き方」が
すべてを決めるのです。
・・・・・・
真本音優柔不断タイプ
について、
そしてそこからの
抜け出し方について
前回まで書かせて
いただきました。
(→前回記事)
思った以上の反響を
いただき、
個別でのご相談等も
いくつもありまして、
少し驚いています。
みんなが言うのです。
「これ、
私のことでは
ありませんか?」
と。
実は、
私自身も文章を書きながら、
これはひょっとして
私自身のことでも
あるかも、
と思ったりもしました。
もしかすると、
今の私達は、
すべての人類は、
真本音優柔不断タイプだったか?
・・・などとも
思い当たりました。
本当は
誰も、
本当の決断をせずに
ここまで
歩いてきてしまったのでは
ないか、と。
だから、
今のような世の中に
なってしまったのでは
ないか、と。
その真偽はともかくとして、
「私は、
真本音優柔不断タイプでは
ないでしょうか?」
と言われた人の多くが、
誰がどう見ても、
すごい決断力を持っている
人達だったのが
笑えました。
そう考えますと、
これまでの自分は
真本音優柔不断タイプだったかも
しれない、
といいう捉え方をし、
だからこそ、
これからはもっともっと
素晴らしい決断をし、
もっともっと人生を
加速させよう、
という意志を持つことは
有意義なことではないかな
とも思います。
とにもかくにも、
すべては
今この瞬間に
自らが決断する
次の一歩、
次の一歩、
で決まります。
それが
真実であり真理
です。
ですから私達は
本当に
「今」
を大事に生きて
まいりましょう。
今、
真本音で
生きる。
やはり最後は
ここに行き着きますね。
つづく
後悔の念とは
向き合えばそれで
OKです。
後悔することで
そのまま自分を責め続ける
方向に行く人がいますが、
その必要はありません。
自分を責め続けたり、
罪悪感の中に
ドップリと浸かっても
自分も周りも誰も
喜びません。
ただ、
後悔の念だけを
しっかりと
味わいます。
それにより
強い刺激が入ります。
特にそれが
真本音レベルの後悔であれば、
その刺激は
自分自身の人生の願いへと
直結します。
しっかりと後悔するからこそ、
そうか、だから自分はこれから
人生において
これを果たしていこう!
という強い想いと共に、
まるで祈りにも似た願いが
湧き起こります。
その願いは、
願うという行為そのものによって
自分の魂も心も
癒してくれます。
自分の魂も心も
開放される感覚を得ます。
それこそが
「真本音の願い」です。
真本音の願いに
行き着いた人は
本当に幸せです。
なぜなら、
自分が何のために
生まれてきたのか?
自分の人生の意味は
何か?
自分という人間の
存在意義は何か?
自分はこれから何を
すれば良いのか?
自分はどこに向かえば
良いのか?
自分は誰と共に
進めば良いのか?
・・・などなど、
あらゆる答えが
「観える」
ようになるからです。
これほど、
私達を根底から安定させてくれる
ものはありません。
そして自分の内側から
パワーを漲らせてくれる
ものはありません。
しかしそこに行き着くためには、
多くの場合、
自分の中にある最大の後悔と
向き合う必要があります。
自分の中の
最も辛いものと
向き合える人は、
すべてと
向き合えるのです。
すべてと向き合えて
初めて、
真本音の願いは
浮上するのです。
・・・・・・
さて、
真本音レベルの後悔と
あなたが
向き合えたとします。
(→前回記事)
その先のステップを
ご紹介します。
真本音レベルの後悔と
向き合うことにより、
あなたの中の真本音は
これまでとは
比べものにならないくらいに
燦然と輝き出すでしょう。
それはまるで
新たな命が
宿ったかのようです。
新しい人生が
今ここから
始まったかのようです。
これまで見えていた景色が
まったく違ったものとして
目に映るでしょう。
結果として、これまで
価値を置いてきたことに
急に興味を失うかも
しれません。
逆に、
これまでまったく
興味も関心もなかったことに
急に価値を見出すかも
しれません。
それらの「変化」には
素直に自分を
委ねてしまいましょう。
「自分は
生まれ変わったのだ」
「ここから新しい人生が
始まるのだ」
と受け止めれば
よいです。
そして、
これまで真本音がまだ
「大地」だった頃に、
すべての行動を「大地」に
確認しながら決めていたように、
ここからも
すべての行動を
「真本音」に確認しながら
決めていきましょう。
遊び心を持ちながら、
で結構です。
一つ一つの自分の
行動、振る舞いのすべてを
頭で考えるのではなく、
惰性で行なうのでもなく、
丁寧に真本音に
問いかけるのです。
「次、何をしよう?」
「今から、これをしようと
思うけど、どう?」
「これをするか、あれをするか、
どちらがいいだろう?」
これを続けることで、
自分のこれまでの
行動パターンが
短期間で壊れていきます。
それはもう
壊してしまってください。
これまでの行動パターンは
すべて、
「優柔不断に生きるため」
のものであったと
あえて
断定してください。
自分を変える、とは
このように
自分の「今、ここ」における
一挙手一投足を
変えていく、
ということなのです。
自分を変える、とは
何かを一気に大きく変える
わけではないのです。
「次の一歩」
「次の一歩」
を一つずつ丁寧に
変えていくだけなのです。
一つ一つを
すべて真本音の通りに
変えることで、
これまでのパターンが
自然に崩れ、
真本音の願いに向かう
自分自身に
だんだんと近づいていきます。
それは
自分にとっては
とても幸せなことです。
真本音の望む通りの
行動を取っている自分。
・・・これが
自然体になっている
ということです。
こういったことを続ければ、
いつしか、
真本音にわざわざ
確認せずとも、
普通に行動すれば
自然に真本音通りに動ける自分に
なっているでしょう。
「本来の自分」に
戻っているでしょう。
そうなって初めて、
私達の中からは
『真の本気』
が湧き出ます。
それこそが
あなたの本当の
姿です。
つづく
昨日の続きです。
真本音優柔不断タイプの人が
自らを解放し、
本来の自分に戻るためのステップを
ここまで、ご紹介してきました。
「最も強い自分の心」を
自分の体の中に
入れ、
そしてそのことにより、
それはその人の
『真本音』
となりました。
つまり、
「真本音を取り戻す」
ことができたのです。
これが昨日までの
ステップです。
(→前回記事)
真本音を取り戻すことが
できましたので、
ここからは
「真本音との対話」
が始まります。
しかしちょっと
待ってください。
その前にどうしても
行なっていただきたいことが
あるのです。
・・・・・・
それは、
「後悔と向き合う」
ことです。
真本音を取り戻した
今だからこそ
できることです。
人は、人生において
本当にたくさんの
後悔を
繰り返します。
その多くは
反応本音レベルのもの
です。
反応本音レベルの後悔
とは、
それを乗り越えることで
自分の成長に
つながります。
つまりは、
乗り越えられるもの。
それが
反応本音レベルの後悔
です。
しかし
いかがでしょうか?
あなたには、
乗り越えられない後悔が
ありませんか?
その後悔からは
逃げたいばかり。
ですからずっと
心の片隅に
それを隠してきました。
記憶の彼方に
それを
取り残してきました。
そんな後悔は
ありませんか?
一言で言えば、
「耐えられない後悔」
です。
「思い出せない後悔」
です。
思い出せないような後悔について
「ありませんか?」と
問われても、
思い出せませんよね、きっと。
しかし、今、
それを思い出して
ほしいのです。
そしてその後悔と
向き合ってほしいのです。
それは
「真本音レベルの後悔」
です。
真本音レベルの後悔は
本当に、
キツイです。
なぜなら、
それは、
自分の心が耐えられる範疇を
逸脱しているからです。
しかし私達の真本音は
わざと自分に
そういった後悔の経験を
させることがあります。
なぜなら
それだけの経験をするからこそ
初めて見つかるものが
あるからです。
それは
「真本音の願い」
への道です。
真本音レベルの後悔を
するからこそ、
真本音の願いへの
道のヒントを
私達は得ることができるのです。
真本音とは
魂の意志である、
とも言えます。
魂そのもの
とも言えます。
真本音を取り戻す
ということは、
あなたの中に魂が
戻ってきたということ。
ですから、
心の視線ではなく、
魂の視線で
耐えられなかった後悔達と
向かい合ってください。
それができた時に
初めて、
あなたの真本音(魂)は
あなた自身に
「OK」
を出すはずです。
そうか、自分はもう
本気で進める自分に
なれたのだな。
自分はもう
真剣に生きる覚悟を
持てたのだな。
そのように
真本音が自ら
判断するのです。
その「判断」が、
自分を解放する
必須条件となります。
・・・・・・
あなたの中に
戻ってきた真本音の場所を
今一度、
特定してください。
ここに確かに
私の真本音は
存在するな、
という実感を
しっかりと得てください。
その上で、
その、自分自身の真本音に
問うてください。
「私の、真の後悔とは
何だろう?」
「君が私に与えた
後悔とは何だろう?」
そして、
あとは静かに
待ってください。
自然に思い出せること
があると思います。
ひょっとすると
心に強烈な抵抗が
走るかもしれません。
しかしその場合は、
自分の真本音(魂)にのみ
意識を向けてください。
泣きたくなれば
泣けばよいです。
わめきたくなれば、
毛布でもかぶって
ご家族などに迷惑をかけないように
わめいてください。
これをしっかりと
行なうことです。
ゆっくりと時間の取れる時に
じっくり行なってみて
ください。
今すぐにやらなければ
ならない、
とか
今日中に完了させねば
ならない、
とか
慌てる必要はありませんので、
「今やろう」
と思えた時に
ぜひ行なってください。
これが完了すれば、
真本音との対話は
随分とやりやすく
なるはずです。
つづく
私達の心の中には
いくつもの願いが
浮かんでは消えていきます。
達成されることで
成就し消える願いもあれば、
達成せずとも
自然に消えてしまう願いも
あります。
願いを持つのが
私達人間の宿命。
願いに生きるのが
人間の本質です。
ただ、
その願いの中で
何があっても、
自分がどれだけ成長しても、
どのような経験を積んでも、
環境がどのように変わっても、
まったく揺るがずに
心の中心に在り続ける
願いがあります。
それは
心の中にある願い
と言うよりも
魂の中に抱いている願い
と言った方が
良いかも知れません。
そしてそれは
願いであるのと同時に
自分自身へのテーマであり
課題でもあります。
その願いでありテーマであり
課題であるものを
私達は人生を通じて
探求・探究しようとします。
それをあえて、
「真本音の願い」
と私は呼んでいます。
真本音優柔不断タイプの人は、
その真本音の願いが
ある意味、ですが、
強過ぎる人なのです。
その願いを自ら
認識してしまうと、
その時の自分の状況を顧みずに
一直線にそこに
向かってしまうのです。
それはある意味
危険なことでもあります。
自分が制御できなく
なるくらいに
その願いが強烈なのです。
ですから、その人は、
・自分自身の準備と
・環境の準備が
整うまで、決して
自分の願いを顕在化しないように
してきました。
願いが強烈な分、
慎重になっているのです、
真本音が。
そのようなタイプの人達に
今回、私が投げている
メッセージが
「もうスタートして大丈夫ですよ」
というものです。
これはある意味、
かなり強烈な
メッセージのはずです。
これをまともに受けた人は
自身の人生が
大きく変わってしまうかも
知れません。
・・・・・・
でも、私は
その覚悟を
持ってほしいと
願っています。
何事も、
タイミングが
大事です。
いえ、
少し極端に言えば、
タイミングこそが
大事で、
タイミングが
すべてです。
恐らく、
真本音優柔不断タイプの人達が
自身の願いを解放し、
自身の本気さを解放するのは
人生で一度きりの
チャンスしかありません。
それが、
今です。
今を逃したら、
恐らく二度とこのチャンスは
来ません。
それくらいに
重要なタイミングが
来ています。
ですからあえて
申し上げます。
「もう大丈夫です。
自分の本気さを
取り戻すチャンスです。
今しかありません」
と。
・・・・・・
真本音優柔不断タイプの人が
自分を解放する方法。
昨日の続きを
お伝えします。
(→前回記事)
「最も強い自分の心」が
自分自身の「大地」となり、
その「大地」と対話をしながら
自身の行動を決める。
・・・というところまで
来ました。
これを続けていただくと、
ある時ある瞬間に、
「大地」から
メッセージがあるはずです。
「もう、君の中に
入ってもいいよ」
というメッセージです。
それがあったら、
「大地」となっていた
「最も強い自分の心」を
自分の体の中に
入れましょう。
ここで大切なのは、
あくまでもこれは
「大地」の判断で、
というところです。
あなたが判断しては
なりません。
あくまで「大地」から自然に
「入ってもいいよ」という
メッセージが来るまでは
決して自分の中には
入れないでください。
「大地」の意志を尊重する
ことが重要ポイントです。
「大地」は
見極めているのです。
あなたの「準備」が
整うことを。
「準備」が整わないのに、
無理に「大地」を自分の中に
入れようとすると、
「大地」の反発を受けます。
するとまた最初から
やり直さなければなりません。
常に「大地」と対話をしながら
「大地」との信頼関係を
築いていくのです。
それは「自分自身」との
信頼関係であり、
「本来の自分」との
信頼関係です。
「大地」のペースに合わせ、
「大地」の言うことを
尊重してください。
そして「大地」が
「もう中に入ってもいいよ」
とメッセージしてくれたら、
体の中に入ってもらいます。
どこに入ってもらうかも
「大地」に決めてもらって
ください。
多くは、
中心軸上のどこかです。
お腹の辺りのケースもあるし、
鳩尾の辺りとか、
胸の中心とか、
喉の辺りとか、
稀に、頭のてっぺんとか、
背中全体とか、
中心軸全体、ということも
あります。
「大地」に任せて
ください。
体のいずれかに入ったら
そこに意識を向ければ、
それはもう「大地」ではなく、
別の形をしているはずです。
その形を特定できると
よいですね。
さて。
あなたの体の中に入った
「最も強い自分の心」。
ここからはもう、それを
あなたの
『真本音』
と表現してよいでしょう。
この時点で
あなたはあなたの真本音を
取り戻すことが
できたのです。
ここからはいよいよ、
真本音との対話
です。
つづく
本当のたくましさとは
何でしょうか?
いつも申し上げることですが、
自分の弱さを
本当に知っている人ほど、
本当のたくましさを
発揮することができます。
人はもともと
たくましいのです。
たくましさとは
生きる力。
どのような現実に
さらされようとも、
着実に自らの力でもって
道を拓いていく力。
自分の命の意味を
よく知り、
自分の命を
燃やし続けようとする
意志。
本当にたくましい人は
軽やかです。
深刻さのカケラも
ありません。
もちろん、
反応本音レベルでは
深刻になってしまうことは
あるでしょう。
でも、どれだけ
そうなっても、
その人と向き合えば、
その深刻さは
まったくもって
表面上だけだとわかります。
ですから私は
そういった人と向き合うと
思わず笑ってしまいます。
失礼なことなのですけど。
で、多くの場合
「あなたはまったくもって
深刻さのカケラもない
人ですね」
とそのままフィードバック
します。
もちろん、これも
笑いながら。
それだけでその人は
反応本音レベルの深刻さを
一瞬にして浄化します。
で、
もともとの明るさを
放ちます。
その明るさは、
「何とでもなりますわ」
と語っているような
空気感です。
それを感じる時、私は、
あぁこの人は本当に
たくましい人だなぁ、
と感嘆します。
真本音優柔不断タイプ
の人は、
もともとはそんな人
ばかりです。
でもその自分のたくましさを
わざと隠しながら
生きて来ました。
「無価値感」
という自分を前面に
出しながら。
(→前回記事)
「無価値感」から
解放された時、
その人は本来のその
明るさと軽さと
たくましさを
まるでカミナリに打たれたかのように
急激に発揮し始めるでしょう。
その、解放のための
方法を
ここ数回はお伝えしています。
では、
前回からの続きです。
・・・・・・
「最も強い自分の心」が
自分の足元に
来ました。
そして、自分自身の
「大地」となりました。
それが前回までです。
その「大地」を
感じ続けることで
あなたは
どのような「心模様」に
なりますか?
恐らく、
「大地」を感じるだけで、
これまでにない心の安定感
を覚えたり、
これまでにない発想が
生まれたりしているでしょう。
まずはその「感覚」を
感じ取ることが
重要です。
そしてその「感覚」と
共に生きることを
してください。
その「感覚」に
慣れてください。
その「感覚」こそが
本来のあなたの安定感です。
これまでの不安定感は
本来ではなかったのです。
充分に「感覚」に慣れた
ところで、
次のステップに進みます。
それは、
「大地との対話」
です。
常に、
「大地」に話しかけて
みてください。
もちろん、
心の中で話しかれば
結構です。
そして、
次の自分の行動を
「大地」に訊いてください。
次の自分の行動を
「大地」に訊いた上で
実際に行動に移すのです。
例えば。
朝、目が覚めたとします。
まず、
「今からすぐに起き上がる?」
と、
「大地」に訊いてください。
「すぐに起き上がる」
と答えが返って来たら、
すぐにベッドから起き上がります。
「もう少しこのままでいる」
と答えが返って来たら、
「大地」が「もう起きよう」と言うまで
そのままでいます。
さて、起き上がりました。
「まず、何をしよう?」
と「大地」に訊きます。
「シャワーを浴びよう」
と「大地」が言えば、
その通りにします。
「ごはんをすぐに食べよう」
と「大地」が言えば、
その通りにします。
このように、
自分の一挙手一投足をすべて
「大地」に訊きながら
決めていくのです。
決して自分の頭で
決めるとか、
いつものパターン通りに
動くとか、
をしないでください。
一つ一つ、
「大地」に訊きながら
です。
最初はちょっと面倒かも
しれませんが、
慣れると楽しくなります。
なぜなら、
これまでの自分とは
明らかに異なる
行動パターンが増えるから
です。
それはちょっとした
冒険です。
しかもその冒険をすると、
確実に
楽しくなります。
どことなく、
イキイキ、ワクワク
して来ます。
なぜならその行動の仕方
こそが、
あなたが本来したかった
行動の仕方だからです。
これまでのあなたの
行動パターンは
「無価値感」によるもの
でした。
そこから抜け出すわけですから
イキイキ、ワクワク
するのは当然です。
さらに、例えば。・・・
家を出る時も、
「今、出る?」
とか
「何時に出る?」
とか、
「大地」に訊きます。
今日は、
どんな服を着るか?も
「大地」に訊きます。
電車に乗る場合も、
どの車両に乗るか?も
「大地」に訊きます。
座席に座るか、
それとも立つか、
どの座席に座るか、
どの辺りに立つか、
なども「大地」に訊きます。
このように
すべて「大地」に訊き、
「大地」に委ねます。
もしどうしても
「大地」の言う通りに
動きたくない場合は
無理をしなくても構いません。
できるところから
「大地」の言う通りに動き、
それを楽しむのが
コツです。
それくらいの気軽さで
これを続ければ、
自然に「無価値感」から
解放されていきます。
自分の新たな
楽しい行動パターンを
見つけられるでしょう。
今日はここまで
とします。
つづく
「無価値感」。
自分に対する「無価値感」。
つまり、
自分という人間には
まったく価値がないのだ、
という思い込み。
「自分には価値がない」
という信念。
そういった「心」は
実は、誰の中にも
存在しています。
多かれ少なかれ。
もちろんそれは
反応本音の一つです。
しかしそれが
とてつもなく大きく育っている
人がいます。
「真本音優柔不断タイプ」
と私が呼んでいる人達は、
その「無価値感」が
非常に強いです。
そういった「無価値感」を
自分自身の「決断」の
ストッパー役として
わざと活用しているのです。
当然ですが、
「無価値感」の強い人は
「決断」できません。
「決断」とは
決断をしようとしている
自分自身を
信じることができて初めて
成し得る行為だからです。
自分を信じない者が
100%の答えを出せる
わけがありません。
だって、
答えを出そうとしている
自分自身を
信じていないわけですから。
「真本音優柔不断タイプ」は
本来は、
決断力も
突進力も開拓力も
とてつもないものを
持っています。
しかしそれをあえて
発揮できないように
してきました。
そのために活用したのが
「無価値感」です。
しかしそれはもう必要
ありません。
もう、自分を解放しても
よいのです。
本気になっても
よいのです。
そのためには、
「無価値感」の中にドップリと
浸かってしまっている
自分自身を、
そこから救い出さねば
なりません。
私が前回から
ご紹介している方法は
そのためのものです。
つまり、
「無価値感から自分を
解放させ、
本気になれる自分を
取り戻す」
ための方法です。
(→前回記事)
以下に、昨日の続きを
ご説明します。
・・・・・・
地球の中心と
自分の中心軸と
宇宙の彼方を結ぶ
「一直線」を
まずは見出しました。
そして、
その「一直線」上の
足元よりもさらに下の方に
「最も強い自分の心」
を見出しました。
ここまでが前回です。
「最も強い自分の心」を
観察してみて
いかがでしょうか?
そこに意識を向けると、
「最も強い自分の心」が
どこかにいなくなってしまった、
という人は
いませんか?
最初は場所を特定できたのに、
意識を向けるようにしたら、
消えてしまった、
とか
別の場所に行ってしまった、
とか。
その場合は、
その「最も強い自分の心」が
逃げているのです。
顕在意識と自分が
つながってしまうことを恐れ、
逃げているのです。
つながってしまうことで、
自分は「本気の自分」に
なってしまう。
それはまずい。
・・・というわけです。
そんな場合は、
「最も強い自分の心」に
メッセージを贈ってください。
「お〜い!
もう私と君は
つながってもいいんだぞ!
もう、
本気の自分になっても
よくなったんだぞ!」
と。
そんなメッセージを
叫びながら、
「最も強い自分の心」の
場所を探してください。
見つけることができたら、
改めて落ち着いて
上記のメッセージを
伝えます。
「もう、私と君は
つながってもよい状態に
なれたようだ。」
と。
そして、次のように
メッセージを続けてください。
「君は、私の中に
入ることができるように
なれたんだ。
もう、こんな下の方で
隠れている必要は
なくなったんだよ。」
と。
さらに続けます。
「でも、いきなり私の中に
入るのは勇気も要るし、
不安もあるだろう。
まずは、
私の足元まで
来てくれないか?
私の足元で
私の大地に
なってくれないか?」
もしこの要望に対して、
「N0」
が返って来たら、
無理をせずにいったん
あきらめます。
そしてまた時間を置いて、
再び同じメッセージを
伝えてください。
「今、伝えるといいかな」
と自然に思えるタイミングで
伝えれば結構です。
それでもまた
断られるかもしれませんが、
何度も続けてください。
何だかんだ言っても
メッセージを伝える相手は
自分自身なのです。
誠意を持って
伝え続ければ、
必ずわかってくれます。
「最も強い自分の心」が・・・
「わかったよ。
じゃあまずは、君の足元まで
行こう。
君の大地のような存在に
なるよ。」
・・・というように
肯定的な返事をくれたら、
さっそく、
足元まで浮上して
もらいましょう。
足元まで来た瞬間に、
あなたはそれを本当に
「大地」のように
感じると思います。
「安定感」が
一気に高まります。
足元にある
「最も強い自分の心」
であり
「大地」であるもの。
その「大地」をしっかり
感じ取ってみてください。
どのような「大地」であるか
をしっかりと観察します。
ある人は、
「高原のような
清々しい大地だ」
と感じるかもしれません。
またある人は、
「広〜く延々と続く
宇宙のように大きな大地だ」
と感じるかもしれません。
感じ方は人それぞれ。
それを感じ取ったら、
どんな時もその「大地」を
感じながら日々を
過ごします。
今日はここまで。
続きは明日です。
つづく
「真本音優柔不断タイプ」
について書かせていただいて
います。
(→前回記事)
自分がこのタイプに
当たるかどうか?
を確かめる方法を
ご紹介している途中です。
昨日ご紹介した方法を
試された人へ、
その続きについて
お話しさせていただきます。
地球の中心と
自分の中心軸と
宇宙の彼方を
結んだ直線がありますね。
その観察をして
いかがでしたか?
まずは、
その直線が途切れることなく
つながっているかどうか?
です。
そして、
つながっていたとして、
それがきちんと「一直線」に
なっているかどうか?
です。
どこかでグニャッと
曲がっている、
とか
どこかで途切れている、
とか
そもそも地球の中心まで
直線がたどり着けない、
とか
宇宙の彼方まで
直線が伸びない、
などの場合は、
真本音優柔不断タイプでは
ありません。
きちんとすべてが
「一直線」で結ばれること
です。
ただし、続きがあります。
「一直線」で結ばれた人は
次に、
その状態で
自分の名前を心の中で
つぶやいてみてください。
フルネームで
つぶやきます。
それを何度か
繰り返します。
名前を繰り返すことで
その「一直線」が
・だんだん細くなる
・どこかが途切れてしまう
・直線ではなく曲線になる
など、
弱々しく不安定な方向に
変化を始めたとします。
その場合、
その人は
真本音優柔不断タイプ
です。
名前をつぶやいても
・何も変化をしない
・むしろ「一直線」がより
強まる方向に変化する
場合は、
その人は
真本音優柔不断タイプでは
ありません。
・・・・・・
自分が
真本音優柔不断タイプ
であると、
もし判明したら、
その人に改めてメッセージ
します。
「もう準備は整いましたから、
本気を出してもいいですよ」
・・・これがメッセージです。
これまであえて
優柔不断に生きてきた、
もしくは
本気を出さずに生きてきた、
そんな自分を
解放してもよい状態と
なりました。
これからは
思う存分に
自分の本来の力を
発揮しながら、
自分の人生の目的を
本気で果たして行けば
よいのです。
ただし、
このタイプのほとんどの人は
そのように言われても
ピンとこないでしょう。
自分の人生の目的も、
どのように本気に
なればよいか、も
さっぱりわからないはずです。
ですからまずは
本来の自分を
取り戻すところから
スタートしなければ
なりません。
そのためのステップを
ここからは
お伝えします。
・・・・・・
もう一度、
地球の中心と
自分の中心軸と
宇宙の彼方を
結んだ「一直線」を
感じます。
そして、
自分の足よりも
さらに下の「一直線」に
意識を向けます。
つまり、
地面よりもさらに下、
地面と地球の中心の間
です。
その、
自分の足よりも下の「一直線」上の
いずれかの地点に、
「最も強い自分の心」
があるはずです。
「最も強い自分の心」は
どこにあるかな?
と自分に問いながら
足よりも下の「一直線」に
意識を向ければ
特定できると思います。
だいたいで結構ですから
場所を特定してください。
例えば、
「地下50mくらいにあるな」
とか
「地球の中心のほぼ近くにあるな」
とか。
「最も強い自分の心」の場所
が何となくわかったら、
その場所に意識を向けます。
そこに
何が観えますか?
自然に浮かんでくる
イメージを捉えてください。
例えば、
「赤色の光が観える」
とか、
「何かゴツゴツした塊が見える」
とか。
人によって
観え方は異なります。
ただここで
大切なのは、
無理なイメージをしない
ことです。
これはイメージを
創り出しているわけでは
ありません。
「実在」を感じ取っている
のです。
自然に感じ取れるもの、
自然に観えるものを
キャッチしてください。
もし何も観えなかったと
しても、
そこに「存在」を感じれば、
それでOKです。
場所が特定できましたら、
しばらくその
「最も強い自分の心」
に意識を向け続けてください。
今日はここまで
とします。
明日まで、
できるだけ多くの時間、
意識を向けてみてください。
つづく
決断のできない自分を
わざと創り出す。
決断のできない自分として
わざと優柔不断に
生き続ける。
それをその人の真本音が
意図して行なう。
もちろん、
本人の顕在意識に
その自覚はまったく
ありません。
ただ、
人生を生きることへの
モチベーションが
高まらないことは
自覚しています。
やろうと思えば
何でもある程度は
できてしまう。
しかし、
本気でとことんそれを
探求したり、
突き詰めたり、
極めることはしない。
どうしても、
そのような意欲が
湧いてこない。
本当はもっと
何かに真剣になりたいのかも
しれないけど、
どうしても真剣になれない。
こなすだけの
日々。
こなすだけの
人生。
こなすだけの
自分。
それが自分であると
心のどこかで
あきらめてしまっている。
しかし
そう思っているのは
顕在意識だけ。
本当は真本音のレベルでは
その人は
着々と
自らの人生のミッションへの
道を
進み続けている。
それが
「真本音優柔不断タイプ」
です。
(→前回記事)
・・・・・・
そのタイプの人の
中には、
言いようのないくらいに
強く、深く、鋭い、
貫くべきものが
あります。
貫くべきものを
その人はずっと
心の奥の奥の奥に
抱き続けています。
決してそれは
その人の顕在意識には
感知できないものです。
貫くべきものを
抱き続ける人。
それが、
あまりにも強過ぎる人。
強過ぎるが故に、
その自分の「本気さ」を
いつ全開にするか?を
とてつもなく慎重に
真本音は見極めています。
その人が
本気を出したら
怖いのです。
その人自身が
自分を止められないくらいに
凄まじいスピードとパワーで
突き進んでしまうのです。
それが激し過ぎるので、
周りの人達が
ついて来れなくなる可能性が
高いです。
いえ、
ついて来れないだけなら
まだよいでしょう。
エネルギーが高過ぎて、
そのエネルギーでもって
周りの人を
傷つけてしまう可能性さえ
あります。
ですからその人は
・・・その人の真本音は
慎重です。
世の中全体の真本音度合い
の高まりを感じ、
安定度を感じ、
人々の本質的な強さを
感じながら、
自分が本気を出してもよい
環境ができあがるのを、
じーっと待っていたのです。
・・・・・・
でも、
準備は整いました。
真本音優柔不断タイプの
人達が、
その優柔不断さから
解放されて、
本気を出せる土壌は
整ったのです。
あとは、
その人達が
自らの本気さを喚起すること。
そして、
自らの強大なエネルギーを
コントロールすること。
それが重要です。
私はその二つの
サポートをすることが
役割です。
・・・・・・
自分は、
真本音優柔不断タイプでは
ないか?
そう思った人へ。
まずは、本当にあなたが
そのタイプかどうかを
確かめる方法を
お伝えします。
以下の通りのことを
してください。
まず立ち上がり、
両足を肩幅くらいに広げます。
気をつけの姿勢で
肩の力を抜きます。
自分のおへその奥の
体の中心と
頭のてっぺんの中心を
結ぶイメージをします。
すると、
体の中に中心軸が
できますね。
その中心軸を、
上の方にずっと
伸ばしていきます。
ずっとずっと伸ばし、
宇宙の彼方まで
無限に伸ばしてください。
それができたら、
次は、
中心軸を
下へ下へと伸ばします。
今度は
地球の中心に
たどり着くまで
伸ばしてください。
地球の中心と
あなた自身の中心軸と
宇宙の彼方が
一本の線で結ばれましたね。
あとは、
その結ばれた一本の線を
観察してください。
そうですね。
できれば、
5分ほど、観察を
続けてください。
そして
その観察した結果を
覚えておいてください。
この続きは
明日書かせていただきます。
つづく
「私、人に対して
無関心なんですよね」
と言いながら、
その人は笑いました。
その笑顔は
とてつもなく無邪気で、
人の心ばかりでなく
魂までもを
癒してくれる、
そんなやさしさに
あふれていました。
その人は
わかっていません。
今のご自分が
しっかりと真本音で決めた
ミッションへの道を
着実に歩んでいることを。
その人は
気づいていません。
ご自分が知らないところで
どれだけ周りの人達に
パワーを与え続けているか、を。
その人は
気にしていません。
自分の道が
正しいかどうか?を。
ただその人は
淡々と
生き続けています。
私はその人に
あえて何も
お伝えしません。
「へぇ・・・、
無関心なんですね」
とオウム返しをしながら
笑うだけです。
何も知らないまま
気づかないままに
進むことこそが
今のその人にとっては
最善の生き方
だからです。
・・・・・・
「決断」とは、
決めて断つこと
です。
一つの道を決めて、
他の道を一切
断つこと。
ひょっとして
あの道もいいかも。
という気持ちが
1%でも残っているうちは
決断したことには
なりません。
表現を少し変えれば、
「決断」とは、
何を断つか?を
決めること。
断つことをせずに
進むならば、
どの選択をしたとしても
ほぼ、行き詰まります。
逆に、
きちんと断つべきを断ち、
一本の道を
決めることができたならば、
どの選択をしたとしても
道は続いて行きます。
どの道を行くか?
どの選択をするか?
よりも、
どの道を行ってもよいから
しっかりと他の道を断つこと
が重要です。
他の道を断つ
潔さ。
これが人生の展開を
決めると言っても
過言ではないでしょう。
・・・・・・
あなたは
自由でしょうか?
「自由」とは
自分自身が
決断できる状態にあること
を言います。
「決断できる状態にあること」
とは、
二つの意味があります。
一つは、
決断できる環境に
いることです。
もう一つは、
決断できる自分で
あることです。
しかし本当のことを言えば、
「決断できる自分」
であれば、
「決断できる環境」
は自ら創り出すことが
できます。
「私は自由ではない」
と言われる人の多くは、
自分で決断できない
ことにより
自由ではない環境を
自ら創り出してしまっています。
・・・・・・
自ら決断できる人
と
自ら決断できない人。
あなたは
どちらですか?
もし決断できないのなら
決断できる自分に
なりましょう。
・・・な〜んてことを
今回は言いたいわけでは
ありません。
実は、・・・
決断することの重要さを
よくわかった上で、
わざと
決断できない自分で
あり続けている人が
いるのです。
そんな人生をその人は
ずっと続けて来ました。
ひょっとすると
生まれた時からずっと。
それは、
その人の真本音が
わざとそうして来たのです。
しかし、
本当にいざ
決断をしなければならない
その瞬間には
「無意識に」
きちんと決断をして来ました。
本人は
気づいていません。
自分が
決断していることを。
気づいていないのに、
肝心要の場面では
間違えずにしっかりと
断つべき道を断っています。
顕在意識の分離。
顕在意識レベルでは
ただ単に惰性で生きている
のですが、
それ以外の部分では
きちんと真本音で
生きている。
そんなタイプの人が
います。
あえて名前をつけると
すれば、
「真本音優柔不断タイプ」
でしょうか。
ここで
あなたに問います。
ひょっとしてあなたは、
真本音優柔不断タイプでは
ありませんか?
そのタイプの人は
顕在意識レベルでは
ほぼ意図せずに
ここまで人生を
歩いて来ました。
流れるままに。
惰性のままに。
しかしそれは
それ自体が
その人の真本音の
望む生き方でした。
なぜ
そのようなことを
するのか?
それにはその人なりの
理由がありますが、
多くの場合は、
「本気にならないため」
です。
世の中の準備が
整うまで、
自分は自分の本気さを
出してはならない、
とその人の真本音は
決めています。
本気さを出しては
ならないが、
その状態のままで
最速スピードで
進もう、
・・・という、
非常に難易度の高い
ことをして来ました。
もう一度、
問います。
あなたは
真本音優柔不断タイプ
ではありませんか?
あっこれ、
私のことだ。
・・・と直観的に思えたら
恐らく本当に
そうだと思います。
今回は
そんなあなたに
私はメッセージします。
メッセージは
単純です。
「準備整ったから、
そろそろ本気を出しても
いいですよ」
です。
とは言え、
本気の出し方を
忘れてしまっているか、
本気の出し方を
全く知らないか。
現時点では、あなたは
そのどちらかだと思います。
真本音で生きて来たけど
本気では生きて来なかった
そんなあなたに、
本気の出し方を
少し解説しなければなりません。
ちょっと長くなったので
次回にて。
つづく
中学3年の卒業式。
私は担任の先生から
『信』
という一文字を筆で書いた
色紙をいただきました。
「君のこれからの人生は、
君が人をどれだけ
信じるか?によって
決まるだろう」
と、その先生は
言われました。
私は恐らく、
中学時代においては
その時初めて、人前で
泣いたのかもしれません。
その「信」の一文字は
ずっと
私の胸の内に
在り続けています。
と同時に、
人を育成するお仕事
というのは
なんて素晴らしいのだろう、
と
その時私は強く
実感したのです。
私事で恐縮ですが、
昨日、5月1日に
私は一つの法人を
立ち上げました。
法人名は
まんま、です。
『株式会社真本音』
超ド直球の屋号と
させていただきました。
約15、6年前に
初めて「真本音」と出会って以来、
ずっと
真本音、真本音、・・・
と言い続けてまいりました。
そろそろ
屋号にしても
バチは当たらないだろう
ということもあるし、
何よりも、
真本音という言葉だけでも
多くの人達に
届けたいとの想いからです。
中学の担任の先生が
私に「信」の文字を
贈ってくださったのは、
私の中に「不信」を
見出したからでしょう。
確かに私は
「不信」の塊でした。
人間不信、です。
人間が怖くて
しょうがなかった。
でもそれを
自分自身でずっと
隠し通してきました。
自分に対して。
私の人生は
「信」と「不信」の
戦いのようでした。
その中で、
随分自分自身と
向き合い続けたな、と
思います。
そして多くの人達と
向き合い続けて
まいりました。
人間の汚い部分、
弱い部分、
絶望的な部分、
どうしようもないところ、
愚か過ぎるところ、
悲し過ぎるところ、
・・・
本当に見たくないものと
随分と
向き合い続けて
まいりました。
本当にこれは
大袈裟な表現では
ないのですが、
あまりに多くのストレスや
悲しみを受け過ぎて、
自分自身の命を
失いかけたことは
数え切れません。
なんで他人のストレスで
この俺が
死ななきゃならんのだ!
と恨みながら
自分の命が
尽きそうになるのを
どうしようもなく
感じた瞬間は、
何度味わっても
それはもう
大変なものでした。
恐らく、
これからもそういった目には
数え切れないくらいに
遭遇するでしょう。
でも、
それだけの目に遭いながらも、
今はようやく
胸を張って
100%の淀みなく、
宣言することが
できるのです。
私は、
「人間」を
信じることができる、
と。
「人の可能性」を
信じることができる、
と。
私は
目の前のその人が
知るよりももっと深く、
その人の愚かさを
知ることができます。
そして、
目の前のその人が
知るよりももっと深く、
その人の可能性を
知ることができます。
その両方を
感じ取れる自分に
なれたことを
本当に感謝します。
・・・・・・
以下については改めて
詳しく書かせていただくことに
なると思いますが、
私達の意識の次元として、
『8次元』
という次元があります。
人は8次元の意識を
思い出すと、
「すべては一つである」
ということ、
そして、
「すべては私自身である」
ということを
理屈ではなく
実感として、感覚として
理解できるように
なります。
本当にそれは
理屈ではなく、
例えば、あらゆる物が
上から下に落ちるのと
同じような摂理として、
当たり前のこととして
受け止めることが
できるようになります。
かと言って人は
8次元の意識を
思い出しても、
4次元の意識も
持っています。
高次元から低次元まで
すべての意識を
同時に持ち続けるのが
私達人間です。
「自分だけが良ければいい」
という4次元と、
「すべては私である」
という8次元。
それが同時に
心の中に存在
するようになります。
たとえ、
8次元を思い出したと
しても。
だからこそ、
私達は
人間にしか創れない世界を
創り出すことが
できるのです。
私の人生の目標は、
すべての人が
8次元の意識を
思い出すこと。
そして、
4次元から8次元まで
すべての次元を
大切にできる世の中を
創り出すこと、
です。
そのための
一つの基点として、
・・・というよりも、
一つの「祈り」として、
株式会社真本音を
スタートさせて
いただきます。
今後ともどうぞ、
よろしくお願い申し上げます。
つづく
謙虚という言葉が
ありますが、
本当に謙虚な人とは、
自分の不甲斐なさや
自分の無力さを
本当の意味で
実感できている人であると
私は思います。
ここで言う
不甲斐なさや無力さとは
思い込みレベル
のものではありません。
自己卑下からくる
ものではありません。
事実です。
事実としての
自分の不甲斐なさや
自分の無力さを
知る者は
自然に謙虚になります。
「謙虚」という言葉を
辞書で引きますと、
「自分の能力や地位に
おごることなく、
素直な態度で
人に接するさま」
とあります。
謙虚さとは
素直さ。
素直さとは、
自分の解釈の世界から
自由になっている状態
です。
この状態になるためには
私達は
「挑戦」をしなければ
なりません。
本当の意味での
挑戦の人生を進んでいる人は
事実として
自分の不甲斐なさや
無力さを
知ることになるからです。
つまり謙虚な人とは、
自分の人生を
素直に進んでいる人
です。
・・・・・・
人が
まぶしく観えますか?
誰と会っても
人が
まぶしく観えますか?
すべての人には
その人独自の
光や輝きがあります。
その光や輝きを
実感できるのは
謙虚な人だけです。
例えば、
劣等感という言葉が
あります。
この言葉は
謙虚さと同義語のように
見られやすいですが、
劣等感とは
傲慢の象徴です。
劣等感とは
優越感と裏表の関係に
あります。
優越感を持ちたいからこそ
劣等感が発生します。
それは、
真の謙虚さとは
まったく関係のないもの
です。
ただし、
毎度申し上げることですが、
劣等感があるからそれを
消しなさい、
ということではありません。
劣等感も優越感も
あるのが人間です。
私も劣等感の塊でしたし。
それは、
傲慢さの塊であった
ということですけどね。
そういった心はすべて
4次元の意識
ですが、
これも何度も申し上げる通り、
4次元の意識があるのが
人間です。
4次元、つまりは
我欲。
我欲があるのが
人間で、
それを失ったら
人間としての存在意義も
失います。
ただし、我欲も
劣等感も優越感も
反応本音です。
反応本音とは
弱く、儚いものです。
状況が変われば、
その状況に反応し
揺らぐ弱い心です。
その心に基づいて
人生を推進させると
弱々で揺れ揺れの
不安定な人生と
なってしまいます。
そこは注意を
したいですね。
・・・・・・
自分の我欲に捕らわれて、
人を見るのではなく、
人とあるがままに
ありのままに
向き合うことこそが
大事です。
そのためには、
自分の内側にいないこと。
意識を
オープンにすることです。
常に外の世界に
意識を向け続けること。
外の世界を
観察し続ける眼差しが
大事です。
「自分が答えを
出せるはずがない」
という劣等感。
「すべての答えは
自分が出すべきだ」
という優越感。
そのどちらも
脆弱なものです。
「共に向き合うからこそ、
今ここで
共に最善の答えを
創造できる」
「だから、
この人との時間を
本当に大切にしよう」
・・・これが
謙虚さです。
私達は
唯一無二の存在。
その私達が、
もう一つの唯一無二の存在と
向き合っています。
唯一無二の存在が
共にここにいる。
・・・これが
人と人がコミュニケーションを
とるということです。
唯一無二同士の
相乗効果。
それは本来であれば、
とてつもないエネルギーを
発生させます。
その事実を知り、
その事実に素直に従う。
これこそが
謙虚さということでは
ないでしょうか。
つづく
心を静かにし、
目を閉じてください。
自分が今、
一本の道を歩いている
イメージをしてください。
自分の人生の道
のイメージです。
過去から今日までの
道。
そして明日から
さらに未来に続く
道。
過去、今、未来・・・。
その3点を同時に
感じてください。
そうした時に
あなたの魂は
静まるでしょうか?
それとも
騒がしくなるでしょうか?
魂が静まるのと
心が静まるのは
本質的に異なります。
例えば、
心が大騒ぎをするような
大都会の雑踏の中にいても、
時折、
魂が非常に静かになる
瞬間があります。
魂の静けさとは、
外部環境から影響を受けるもの
ではありません。
それよりも、
自分自身の生き方、
自分自身の
意思の持ち方、
そして、
自分自身の
願いの持ち方によって
魂は騒がしくなったり
静かになったりします。
要するに
内面的な理由です。
そこでもう一度。
自分の人生の道を
イメージした時、
自分の過去、今、未来の
3点を感じた時、
あなたの魂は
静かになるでしょうか?
もし
静かになれば、
今のあなたの生き方と行き方に
あなたの魂は
納得しています。
もし騒がしくなるのであれば、
あなたは
自分が本当に望む
生き方と行き方とは別の
生き方と行き方を
しているのでしょう。
その場合は、
何が問題なのだろうか?
と、
自分自身に問うてみて
ください。
自分の心に問うのではなく、
自分の魂に
問うのです。
・・・・・・
魂が静まる道。
それは、
現実レベルでは
冒険の道、である可能性が
高いです。
つまりは、
ハラハラドキドキするような
道です。
これまで
やったことのないことに
挑戦する。
自分にはできない、と
思い込んでいたことを
やってみる。
未開の地に
一歩ずつでも
進んでみる。
本質的には、そのような道を
望んでいる人が
多いからです。
この傾向は、
今年に入ってから
飛躍的に高まりました。
今の多くの人達の
人生の潮流は
「冒険」
です。
冒険すればするほど、
私達の魂は
静かになります。
それが望む
生き方であり、
行き方だからです。
冒険しようとすると、
「いやいや、私は安定がいい!」
という心が
反動のように発生するでしょう。
人は皆、
安定を求める生き物でも
あります。
しかし、
冒険を止める安定とは
反応本音に過ぎません。
なぜなら、
真の安定とは
冒険の中にこそあるからです。
冒険をせずに
同じところに止まり続けることで
私達の心は安心するかも
しれませんが、
私達の魂は
逆に不安定になります。
その不安定さを
打ち消そうとして、
さらに私達は止まって
しまいます。
しかし止まれば止まるほど、
さらに魂は不安定に
なります。
そしてさらにその人は
止まり・・・。
挑戦をしない人ほど
弱くなるのは、
挑戦をしないという
経験不足が招いている
からではありません。
挑戦をしない、
冒険をしない、
ということによる
魂の不安定さが
その根本原因です。
私達の魂は
もともと冒険を望んでおり、
というよりも、
冒険するために生まれたのが
「人間」という存在であり、
その本来の生き方を
取り戻そうという意志が
ニョキニョキと
芽生えてきているのが、
今年に入ってからの
傾向なのです。
つまりは、
自分自身に本当に
素直に生きるということを
すれば、
私達は自然に冒険の道に
入っていくことになります。
・・・・・・
「冒険」とは、
表現を変えれば、
既存の何かを壊し、
新たな何かを創造する
ということです。
「壊す」
という表現をすると
さらに怖さや不安が
増すかもしれません。
しかしやはりそれも
反応本音です。
今、
私達の中には
壊したいものが
あるはずです。
その衝動に
素直になることが
冒険への第一歩です。
魂の衝動。
これも最近、
本当によく感じることです。
魂の衝動に
今、
突き動かされようとしている人が
激増しています。
そんな時は
その衝動に
素直になることです。
怖いかもしれません。
でも、
素直になることです。
そうすれば、
一気に自分が
変わります。
そして、
一気に
安定を得ます。
ドッシリと
構えることができるように
なります。
真の安定とは
こういうことだったか、と
わかります。
冒険を
躊躇している人へ。
その躊躇は横に置き、
一歩を踏み出して
みましょう。
今が、
人生を変えるチャンス
です。
つづく
人の人生の主導権を
奪ってしまうサポートを
サポートとは言いません。
傲慢と言います。
傲慢な人ほど、
自分の傲慢さに気づかない
という傾向があります。
「傲慢」
とはとても厄介で、
私も随分と
その中にドップリと
陥りました。
陥っているときは
気持ちよくてしょうがない。
というところが
「傲慢」の
厄介なところです。
魂の本当の悦びと、
傲慢さ故の喜びの
区別がなかなかつかないのが
私達人間の性(さが)の
一つです。
・・・・・・
当たり前のことですが、
すべての人には
各々の個性が
あります。
自分とまったく同じ個性を
持った人というのは
世の中には一人も
いません。
もちろん、
過去にもいませんし、
未来にもいません。
人類の全歴史の中で、
「自分」という人間は
たった一人です。
唯一無二の
存在。
それが私達です。
ではなぜ、
まったく同じ個性が
この世にはないのでしょうか?
なぜ私達は
唯一無二の存在
なのでしょうか?
その答えは
シンプルです。
私達には
「違い」
が必要だからです。
「違い」があることで初めて、
私達は進化を遂げる
ことができるからです。
「違い」は必ず
多かれ少なかれ
不協和音を生みます。
ズレの気持ち悪さを
生みます。
それこそが
大切です。
ズレの気持ち悪さによって
私達は試行錯誤を
始めます。
どうすればこの、
気持ち悪さが
なくなるのだろうか?
どうすれば、
私はもっと
楽になれるだろうか?
気持ち悪さを
感じれば感じるほど、
その問いは
強いものとなります。
その結果、
本気で
試行錯誤に取り組むように
なります。
本当は
何が大事なのだろうか?
どうすれば、
私達はお互いに
もっと楽になり、
もっと幸せになれるのだろうか?
そういった
試行錯誤を繰り返すように
なった意識が
「5次元」
の意識です。
4次元の意識とは
「我欲」でした。
5次元の意識は
その我欲から一歩踏み出し、
試行に入ります。
ですから私は5次元を称して
『試行の次元』
と呼んでいます。
今のこの世の中で
最も主流を占めているのが
この試行の次元、
つまり5次元の意識です。
ある意味、
4次元の意識でいる方が
楽です。
物事を断定的に
迷いなく捉えることも
できます。
(あくまでも、反応本音レベル
においてでは、ですが。)
しかし
試行の次元に意識が上がることで
様々なことに
本気で迷うようになります。
悩みが増えます。
もちろん
4次元の意識でも
悩みは尽きません。
しかし4次元の悩みとは、
あくまでも
自分だけが良くなるには
どうすればよいか?
自分を守るためには
どうすればよいか?
という、
自分本位の悩みです。
それに対して5次元の悩みとは
本当に大切なものを
求める悩みです。
進化のための
悩みです。
進化のための悩みに
正面から向かい合うことで
私達は、
魂レベルでは
パワーが高まります。
4次元で生きることは
心のレベルでは
ある意味、元気になるかも
しれませんが、
魂のレベルでは
延々とパワーの枯渇が
続きます。
ということで言えば、
魂のパワーやエネルギーを
取り戻し始めるのが
5次元の意識
と言ってもよいでしょう。
・・・・・・
多くの人達が
5次元の意識で
試行錯誤を続けているのですから、
その人にとって
最も必要な試行錯誤が
できる状態にする。
それが本当の
サポートです。
しかし、
その人の試行錯誤を奪い取り、
安易に
「この場合はこうすれば
よいのですよ」
と答えを与えてしまうような
サポートをしている人が
多いのも事実です。
さきほども書きました通り、
それはサポートとは
言えません。
人にとって大切な
試行錯誤を奪い取るのは、
その人の人生や命を
搾取しているのと
同じことなのです。
ですから私のコーチングは
いかにその人(その組織)を
成功させるか?
ではありません。
いかにその人(その組織)が
最高の試行錯誤ができるか?
こそを、
最も大切にしています。
こういった本質を
理解しているコーチが、
世の中にはもっともっと
必要かな。
つづく
泉からトツトツと
水が湧き続けるように、
自分の中からトツトツと
言葉が湧き続けることが
あります。
頭で考えている
わけではなく。
何かを説明しようと
しているわけではなく。
何かを理解してもらおうと
思っているわけではなく。
何らかの意図を
持っているわけではなく。
ただ、
トツトツと
ゆっくりと
湧き続ける言葉達が
あります。
それを私は一つずつ
宝物のように
抱き、愛でながら、
何の解釈も色もつけずに
そのまま
口に出します。
それはまるで
自分がただの
スピーカーになったような
感覚です。
自分で言葉を
口にしながらも、
自分自身も
それを聴いて
楽しんでいます。
次の一言を
自分の口は
何を語るのか?
を楽しみながら、
私は目の前のAさんに
向かって、
トツトツと言葉の一つ一つを
プレゼントします。
やはりそれは
何をどう観ても
私自身の言葉だとは
思えません。
どう観ても、
それは、Aさん自身の
言葉です。
Aさんの
真本音の言葉。
本当はAさん自身が
自力で気づきたい
答え達。
それを私は
Aさんの代わりに
Aさん自身に
お伝えしている。
それだけのこと
のようです。
研修でもコーチングでも
よく皆さんから
おっしゃっていただく
嬉しいお声があります。
「たけうちさんの言葉は
どうしてこんなに
スーッと心の中に
入ってくるんだろう?」
それは
私の言葉では
ないからです。
あなた自身の
真本音の
言葉達だからです。
・・・・・・
皆さんの中にも
「泉」
があるはずです。
その泉は、
地下水脈に
つながっています。
その地下水脈は
目の前のAさんと
共有している
地下水脈です。
地下水脈から
トツトツと
湧き出される
泉を
一つ一つ言葉にする。
そんなコミュニケーションは
本当は
誰もが取れるはずです。
私はこれを
『真本音コミュニケーション』
と呼んでいます。
本当にいつも私は
お会いする人達に
伝え続けています。
真本音コミュニケーションは
私特有の力では
ありません。
人類すべての人が
もともと持っている
普通の力です、と。
ただ、私達は
頭で考え過ぎて
しまうのです。
意図を持ち過ぎて
しまうのです。
自分の考えを
わかってもらおうと
欲し過ぎてしまうのです。
そういった気持ちも
もちろん人間ですから
ありますし、
そういった気持ちは
そういった気持ちとして
大事にすれば
よいでしょう。
しかしちょっとだけ
それらを横に置き、
ただ、
目の前のAさんにのみ
意識を向けて
みてください。
意識を
向け続けて
みてください。
すると、
すぐに「泉」に
気づくはずです。
あとはただ、
その「泉」の言葉だけを
語るようにして、
ただ、
静かに黙っていれば
よいのです。
それだけで
すべての事は
済んでしまいます。
何の説明も
言い合いも
必要なく、
ただ、
泉の言葉をそこに
残せば
よいのです。
それですべては
調和して
行きます。
そんなシンプルな
コミュニケーションライフを
あなたも
楽しんでみませんか?
つづく
今、
これまでの人生を
振り返った時、
最も重要だったなと
思える出来事は
何ですか?
そう自分に問いかけて、
直観的に浮かぶ
出来事を
観てみましょう。
その時の場面を
ありありと
思い出してみてください。
もし可能であれば、
その場面を
イメージの中で
もう一度、
体験し直してみてください。
まるで今ここで
その出来事が
行われていかのるように
イメージするのです。
イメージの世界に
入ってしまうのです。
そして、
その場面の中の
自分の心に
意識を向けてみてください。
意識を向けるというのは
客観的に観察してみる
ということです。
その時の自分の心は
どのように動き、
どのように揺らぎ、
どのような刺激を受け、
どのように変化しましたか?
変化の前は
どのような心で、
変化の後は
どのような心ですか?
その変化によって
その後の日々に
どのような影響が
現れましたか?
もしその出来事がなくて、
自分の心が
それ以前のままだったら、
人生の展開は
どうなったでしょうか?
その変化によって
得られたものと
失ったものとは
何でしょうか?
そしてその変化は
次にどのような変化を
自分自身に
もたらしたでしょうか?
・・・・・・
時間とは、
過去から今、そして未来へと
一方向に流れていきます。
しかしそれは
この3次元の世界だけの
特有の摂理です。
一方向に流れるが故に
私達は
未来を知ることができません。
未来がわからない
という
言いようのない不安と
不安定感。
それがこの世界の
特徴の一つです。
未来がわからない
私達。
しかし、
そんな私達だからこそ
得られたものが
あります。
それは、
「エネルギーの自由奔放」
です。
未来がわかっていれば
私達はその未来に向かって
エネルギーを集約して
行けばよいでしょう。
しかし私達には
集約の方向がわかりません。
それにより
「迷う」
という状態に入ります。
迷うことで発生するのは
エネルギーの分散
です。
あっちにもこっちにも
エネルギーを分散させながら
私達は生き続け、
そのうちにエネルギーの
集約の方法すら
忘れてしまいました。
しかしそれにより
エネルギーは
自由奔放となりました。
悪い言い方をすれば
無駄なエネルギーが
飛び散っている状態。
でも良い言い方をすれば、
そこかしこに
エネルギーが
漂っています。
漂っているエネルギーを
漂ったままにしてしまうのは
もったいないことです。
もし漂っているエネルギーを
集めることができれば、
私達は
想定外の莫大な
エネルギーを
活用できるかも
しれません。
・・・・・・
この3次元の世界は
すべてが分離しているが
故に、
「想定外」の宝庫です。
本来であれば
調和すべきところで
不調和が起き、
本来は平穏に進むべきところで
混乱が起きています。
しかしその「想定外」こそが
この世界の魅力であり、
「意味」であり
「存在意義」でもあります。
「想定外」の中で
私達は何をするか?
何をすることで、
「想定外」だからこそ
生み出せるものを
生み出すか?
この世界でしか
できないことは何か?
これが、
私達全員に共通する
真本音のテーマです。
この世界に
漂っている人のエネルギー。
本当はそこにあるのに、
使われなくなってしまった
エネルギー。
それを私は発掘し、
未来に向けて活用しようと
思います。
私が行なっている活動とは
人のエネルギーをいかに
高めるか?
ということよりも、
そこにあるのに上手く
使われていないエネルギーを
いかに掘り起こして
活用するか?
ということなのだと
思います。
・・・・・・
さて、
最初の問いに戻ります。
これまでの人生を
振り返った時、
最も重要だったなと
思える出来事は
何ですか?
その出来事を
もう一度、イメージの中で
再体験しながら、
自分の心に
目を向けてみてください。
そして今度は、
心のエネルギーの変化
という視点で、
観察してみてください。
その体験により、
あなたの心のエネルギーは
高まりましたか?
低くなりましたか?
高まったエネルギーは
その後、どのように
使われましたか?
低くなってしまった場合は、
そこで奪われたエネルギーは
どこに放出され、
今はどこを漂っていますか?
そのエネルギーを
取り戻すには
どうすればよいでしょうか?
つづく
刹那的な興奮のみを
求めて生きる人は
残念ながら
真本音の悦びを感じることは
滅多にないでしょう。
もちろん、
刹那的な興奮が
いけないわけではありません。
しかし
それは多くの場合
4次元の喜びです。
4次元とは
「我欲」。
自分だけが嬉しければ
それでよし、
とする私達の心です。
私が
「我欲の次元」
と呼んでいるこの4次元は
実在(心の中)の世界においては
最低次元に当たります。
念のために申しますが、
我欲がいけないわけでは
ありません。
それに、
どれだけ高次元の自分に
なれたとしても、
人の心の中から我欲が、
つまりは4次元の意識が
消え去ることは
あり得ません。
我欲があってこその
私達であり、
我欲があってこその
人間であり、
いつも申していますが、
高次元から低次元まで
様々な意識を持つことにこそ
私は、
人間の尊厳と
存在意義を感じます。
我欲は我欲。
それ自体が
良いとか、悪いとか、
そういったことではなく、
我欲は我欲。
ただそれだけの
ことです。
ただし、
この4次元の意識には
私達の真本音は
ありません。
4次元の意識達は
とても儚く、薄く、
すぐに消えてしまうもの。
実在の世界においては
最も弱い存在です。
だからこそ、
我欲のみの喜びとか、
刹那的な興奮のみを
求めて生きる人は
心が脆弱になっていきます。
安定がなくなります。
揺らぎが大きくなります。
心の振れ幅が
大きくなり、
常に何かに怯えながら
生きることになります。
その状態において、
真本音の悦びを
感じることは相当に
難しくなるのです。
・・・・・・
逆に、
「我欲」を否定する人も
います。
実は、
我欲を否定する意識は
我欲と同じ次元に
属します。
何かを否定する、
とは
その時点でその「何か」と
同じ次元であり
同レベルなのです。
昔の私も
我欲を否定していた時期が
ありました。
そして自分は
高尚な人格者であろう
とし続けていました。
その結果、
我欲にフタをし続け、
我欲がそこにたくさん
あるにも関わらず、
我欲をないものとし、
自分が綺麗だと思う心のみに
光を当てて生きていました。
その結果、
体を壊してしまったのですが、
あの時の私は
今思い返しても
非常に不自然でした。
不自然な生き方を
している人は、
その反動が凄いです。
我欲を否定し続けている人は
何かのきっかけで
自分で抑え付けていた我欲が
一気に溢れ出てしまうことが
あります。
いえ、
何かのきっかけがなくても、
抑え続けている我欲が、
どんな時も、
その人の持つ空気感として
滲み出続けることになります。
本人は
我欲を否定しているのに、
我欲の空気感が
滲み出るのです。
そして周りの人達は
その空気感を敏感に
察知します。
何となく、あの人、
嫌だな。
と周りの人は
そんな印象を持ち、
しかし本人は
自分がそのような空気感を
出しているとは
思いもよりません。
そんないびつな人間関係を
日々、創り出してしまう
という結果になります。
いびつな人間関係は
いびつな人生に
直結しますね。
・・・・・・
自分は特別な人間だ、
と思うのも
我欲です。
かと言って、
自分は皆と同じでありたい
というのも我欲です。
そんなこと
どちらでもいいじゃないですか。
最初から私達には
高次元から低次元まで
様々な意識が
あるのです。
大事なのは
自己統合です。
高次元から低次元の
すべての自分が
同じ方向を向いて
パワーを集約する時、
私達は素晴らしい展開を
現実世界に起こすことが
できます。
「俺がやってやったぞ!」
でもなく、
「所詮、僕には無理だ」
でもなく、
ただただ淡々と
生きていく。
それが最も自然
なのですが、
しかしその
「淡々と生きる」
ということは、
高次元の自分にしか
できないことなのです。
「淡々」という言い方をすると
情熱も何もないような
印象になるかもしれませんが、
真の「淡々と」というのは、
安定の象徴です。
安定とは、
その根底に
莫大なエネルギーがなければ
実現し得ないものです。
本当の意味での
「淡々と」を実現できている人は
エネルギーの高い人
なのです。
エネルギーが高い、
とは
心も魂も満ち足りている状態
です。
そうなった時に初めて、
私達は
私達自身の我欲も
許すことができるのです、
本当の意味で。
高次元の自分が
現れれば現れるほど、
低次元の自分も
大切にすることが
できます。
低次元の自分を
否定し拒絶するのは
低次元の自分だけです。
つまり、
本当の意味で
人間らしく生きるためには
高次元の自分を
思い出す必要がある
ということですね。
つづく
私達人間の持つ
大いなる力を一つ挙げよ、
と言われたら、
私は
「再生する力」
であると答えるでしょう。
「再生」という言葉の意味は、
死んだものが生き返ること
ということなのですが、
要するに、
「やり直しが効く」
ということです。
私が出会うクライアントさんは
真面目な人が
多いです。
真面目な人は皆、
真剣に「後悔」をします。
「自分のせい」
にします。
他人のせいにするよりも
まずは自分を責めます。
決してそれが良いことであると
私は思っていません。
自分を責め続けることで
自己満足をしている人も
いますし、
自分を責め続けることで
自分が本来為すべきことに
まったく手をつけられない
という人もいるからです。
しかしそういうことを
差し引いても、
「自分が悪いのではないか」
「自分が別の選択をしたら
良かったのではないか」
という見方をする人は、
どうしても応援したく
なりますね。
そういう人達に
必ずお伝えするのが
「再生の力」
です。
人は、
何かの大きな失敗を
犯したとしても、
きちんと後悔と
反省をするならば、
必ず再スタートを切ることが
でき、
進化の道を歩むことが
できるのです。
100積み上げたものが
すべて壊れて
0に戻ってしまったとしても、
また1、2、3、・・・と
一つずつ積み上げることが
できるのです。
そして
そのように「進み続ける」
ということ自体に
私は大いなる価値があると
思いますし、
「進み続ける」人は
その人なりの充実感と
幸せを得ることができるのです。
問題は・・・、
進んでいるつもりに
なっている人。
本当はまったく進まない
どころか、
人の足を引っ張ることに
エネルギーを費やしながらも
その自覚がまったく
ない人です。
・・・・・・
自己満足。
私も随分と
その状態で生きて
きました。
自己満足に陥っているときは
本人には
まったくその自覚は
ありません。
私は自己満足では
ないか?
という問いが発生した時点で
大丈夫なのです。
問題は、
そういった問いや
視点がまったく
生まれない人です。
その人が
本人の自覚のないところで
周りの人達のエネルギーを
いかに奪い取っているか。
周りの人達の
真本音度合いを
いかに奪い取っているか。
そしてそれが
組織であれば、
その人のために
いかに組織が疲弊しているか。
それを
その人本人にご理解
いただくのは
至難の業でです。
しかしそれでも
やらねばならない時が
あります。
その組織の生死が
かかっている時です。
こういうときは
「第3者」が
役に立ちます。
「第3者」とは
私のような者です。
つまり、
組織に属さないけど、
その組織に深く関わる者
です。
・・・・・・
いったいこれまで私は
どれだけ多くの人達の
心を壊してきたでしょうか。
「あなたは間違っている」
「あなたの生き方そのものが
完全に自己満足だ」
そういった
普通の人には言えない一言を
私はこれまで
どれだけ多くの人達に
ダイレクトに
お伝えしてきたでしょうか。
それをお伝えするたびに
私の心は
ズタボロになります。
それはつまり、
相手の心のズタボロを
そのまま受け取っているのです。
それはとても
つらい行為です。
でも一方で
私はわかっています。
それをすることで
その人の実在が
輝くことを。
心はズタボロでも、
その人の魂が
一気に輝きを放つことを。
その人の心から
魂が
解放されるその
爽快さを。
自己満足をしている人は
自分を誰かが
躊躇なく責めてくれることを
望んでいます。
・・・いえ、
それは「望む」などという
生易しいものでは
ありません。
それは、
「祈る」
と言ってもよいでしょう。
私はその「祈り」を
感じ取ったとき、
私自身の人としての心を
いったん横に置いて、
魂だけの自分となり、
魂の言葉を
その人に直接
浴びせます。
それが私の役割の
一つであると
思っています。
・・・・・・
どれだけ心を
壊されても、
その人の魂の光が
健全であれば、
その人は間違いなく
再生します。
「破壊者」。
時々、私は自分のことを
そう思います。
でも、
徹底的な破壊なくして
本来の創造は
あり得ません。
一番いけないのは
中途半端な
破壊です。
一度、すべてを更地に
するからこそ、
その後に健全な
建物を建てることが
できるのです。
高次元の私は
目の前のその人が
私自身であることを
よくわかっています。
私は私自身に対して
徹底的な破壊を
行ないます。
私自身が
再生することを
祈りながら。
それが私の役割の
一つです。
第3者だからこそ
できることです。
つづく
3次元の世界に住む
私達の目は、
何かと何かをすべて
分離して捉えています。
例えば、
私とあなた。
私とパソコン。
パソコンとマウス。
マウスと書類。
書類とコーヒーカップ。
コーヒーカップとコーヒー。
コーヒーと時計。
時計と壁。
壁と窓。
窓と隣の建物。
・・・
すべてが分離され
区別された世界。
それがこの
3次元の世界です。
ここで私達が見ているものは
すべて
私達の脳が感知している
ものです。
脳が感知できないものは
私達は感知できません。
そしてその脳そのものが
3次元のもの。
3次元世界のための
もの。
最近は脳科学もかなり
進んできたようですが、
それでもまだ私達は
脳のことについて
1%も理解できていない
と聞きます。
間違ってならないのは、
脳の理解が
人の理解である、
と思い込むことです。
あくまで、
脳の理解とは、
この3次元世界の理解に
過ぎません。
・・・・・・
3次元世界に生きているから
3次元のことを理解できれば
いいではないか。
という考え方もあるでしょう。
しかし、
私達の実在、つまりは
心の中の世界とは
4次元以上の世界です。
最低次元は4次元。
そこから
5次元、6次元、7次元・・・
と階層ができています。
実は、
そういった数字を当てて
「階層ができている」
という捉え方そのものが
3次元的理解なのですが、
それは
3次元で生きる私達には
3次元での表現の範疇でしか
物事の理屈的理解はできませんので、
致し方ありません。
3次元以上のことを
3次元世界において少しでも理解するには
3次元表現をするしか
ありません。
ただ、
真本音度合いが高まり
意識の次元が高まることで
頭(理屈)での理解を超えて、
感覚や実感として
私達は4次元以上の世界を
理解できるようになります。
それは、
「理解」というよりも
「思い出す」という
表現がぴったりです。
そうです。
私達は
忘れてしまっている
だけなのです。
この3次元の世界の
中で。
・・・・・・
実在の世界、
つまり心の中の世界とは
最低次元が
4次元です。
そして
5次元、6次元、7次元、・・・
と上がっていって、
最高次元はそれこそ
無限大と言ってよいでしょう。
無限大とはつまり、
3次元における数字では
表現しきれない
ということです。
それくらいに
私達の心の中というのは
広くて深いのです。
それが
人の可能性でもあります。
人の可能性は無限大、
とよく言われますが、
本当にそうであることを
私はよく理解できます。
ただ、
先ほども書きましたとおり、
3次元に住む私達は
3次元の見方しかできませんので、
その範疇に留まります。
つまり
3次元的に考えられる
発想の中で、
さらに3次元的な
「限界」を
自ら設定し、
その中で細々と
生きています。
そうです。
細々と、です。
・・・・・・
限界を、
超えましょう。
そろそろ。
私達は私達の
限界を超えたがって
います。
それが私達の
真本音の共通の
意志です。
ここまでの世の中は
ほぼすべてと言って
よいですが、
3次元世界の中でいかに
上手く生きていくか?
という3次元発想に
基づいています。
人としての
生き方もそう。
ビジネスの仕方も
経営の仕方も
すべて、
3次元世界の中で
いかに上手く生きていくか?
に基づき
開発されてきました。
3次元世界における
成功者とは
そのやり方を上手く
実践できた人達です。
ただ、
もう誰もがすでに
わかり始めているように、
それらのやり方では
それこそもう「限界」が
きているのです。
私達はやり方を
抜本的に
変えていかなければ
なりません。
そうしないと
この世界は
どうなってしまうのか?
という危機感を
持ち始めているのが
今の私達です。
私達は
危機感を
共有しています。
しかしその危機感に
対して、
これまでと同様の
3次元的発想で
対処していては、
何も解決できません。
これまでの私達は
3次元という現象(現実)の
世界の中で、
3次元的発想によって
生きてきました。
しかしこれからは、
実在の世界における
できるだけ高い次元の
意識ややり方を
この3次元世界に
反映させていく必要が
あります。
3次元の世界に
高次元のやり方を
持ち込むのです。
それによってのみ、
これまで解決できなかった
様々な問題が
一気に解決できる
可能性が広がります。
そしてそのやり方は
すべての私達が
心の中ではすでに
わかっていることばかり
なのです。
答えはわかっているが、
忘れてしまっている。
それだけのこと。
忘れてしまっていることを
思い出す。
それが私達の
本質的テーマです。
高次元の話をしますと、
ついつい人は
「現実とはつまらないものだ」
と考えがちです。
しかし
そうではありません。
私達はこの
現実世界に生きていますから、
今、目の前にある
「現実」を大切にすることが
私達自身を大切にすること
です。
高次元で生きる、とは
現実から離れることではなく、
ますます
現実に向かい合っていく
ことです。
高次元の意識で
現実に向かい合い、
高次元のやり方で
一つずつ現実を
変えていく。
それが今の私達が
為すべきことです。
私はこれまでも
そしてこれからも、
そのためのサポートを
し続けます。
そして、
私と同じく
そのためのサポート役を
したいと思っている
人達が今、
増えています。
そんな人達に、
「サポートのやり方」
をお伝えするのが、
私のミッションです。
サポート役の
サポート役かな。
そのための活動を
さらに増やしていこうかと
考えています。
つづく
1対1の会話や、
複数人のミーティングの場で
皆が沈黙してしまう瞬間が
ありますね。
沈黙の時、
いつもどうしていますか?
沈黙の時間は
ちょっと居心地が悪く
なりますね。
緊張感が高まってしまう
こともあります。
それが何となく嫌なので、
沈黙を避けるように
その場を盛り上げたり、
何か話題を提供する人が
出たりします。
1対1の場合は、
沈黙が怖くて
延々と喋り続ける人も
いますね。
沈黙。
確かに、
ちょっと怖いかも
しれません。
でも私はこの
沈黙の時間こそを
大切にしています。
沈黙の間に
「実在」が大きく活性化する
場合が多いからです。
・・・・・・
これまでの傾向として、
実在を感じ取ることが
できるようになればなるほど、
口数が減る人が
多いようです。
無駄な一言が
なくなっていくのです。
場を取り繕うための
言葉が
ほぼ、なくなります。
建前もなくなります。
おべっかも迎合も
なくなっていきます。
結果、
その人は沈黙することが
多くなります。
沈黙しても
不安はありません。
実在を感じ取って
いるからです。
実在を感じ取るということは
目の前の人との
つながりを感じ取るという
ことです。
さらに、
目の前の人との
エネルギーの交換や循環も
感じ取れます。
その安心感が土台にあるため、
表面上の言葉のやりとりが
どのようなものであったとしても、
それに揺らされることは
ありません。
例えば、少し極端に言えば、
目の前の人が自分に
何か批判的な言葉を投げて
きたとしても、
実在レベルでその人との
エネルギーの循環が
とても気持ちよく、
その人と自分との
あたたかなつながりを
感じ取れていたとしたら、
表面上において
どのような批判をされたとしても、
その場はとても
居心地のよいものとなります。
表面上のやりとりだけが
コミュニケーションでは
ありません。
実在レベルでの
コミュニケーションを
私達は誰とでもいつも
とっており、
実はそちらの方が
圧倒的に影響力が
大きかったりします。
端的に言えば、
実在レベルでは
「好き」
と言いながらも、
現実レベルでは
「嫌い」
と言うこともあります。
そこでもし
実在レベルを感じ取れて
いれば、
「何言ってるんだよ」
と笑いながら受け止める
ことができるのです。
その余裕とゆとりが
人生の展開を
大きく変えていきますね。
・・・・・・
私達の人生は、
一つ一つの
人とのコミュニケーションによって
大きく変わります。
実在コミュニケーション力を
持つことは、
人生を非常に
豊かにしてくれます。
誤解とか齟齬が
激減します。
人に裏切られる怖さよりも、
人との本質的なつながりの
深さに驚く悦びの経験が
圧倒的に増えていくでしょう。
・・・・・・
以下は、
話をわかりやすくするための
喩え話だと受け取ってください。
私は、
Aさんと向き合う時、
現象(現実)のAさんと
実在のAさんを
同時に感じ取ることができます。
それは、
現実のAさんの隣に
実在のAさんが立っている
ような感覚です。
ですから私はいつも
二人のAさんと会話をします。
もちろん
私の口から出る言葉は
現実のAさんに向けたものです。
しかしその一方で、
実在のAさんにも私は
心の中で常に言葉を
投げかけ、
実在のAさんとも会話を
しています。
私のコーチングは、
まずは実在のAさんに
訊くのです。
「次、どんな質問を
投げたらいいですか?」
すると、
実在のAさんが答えます。
「では、〜〜という質問を
私に投げてください。」
私はその通りの質問を
現実のAさんに投げます。
それに対して
現実のAさんが
お答えになります。
「どう?この答えは?」
と私は実在のAさんに
問います。
実在のAさんは例えば、
「う〜ん、まだまだだねぇ。
全然素直な答えじゃないねぇ・・・。
では、こんなメッセージを
私に伝えてください」
と、
次に私が投げるべき言葉を
教えてくれます。
私はその通りのメッセージを
現実のAさんに
投げます。
そして現実のAさんから
返ってきた言葉を
実在のAさんに確認し、
さらに次に
何をすればよいかを
相談します。
時々、実在のAさんにも
次はどうすればよいかが
わからなくなることもあり、
二人でう〜む、と悩むことも
あります。
でもこのように
実在のAさんと相談しながら
現実のAさんに関われば、
現実のAさんは
自分自身の真本音に
非常にたどり着きやすく
なるのです。
これがいつもの
私のコーチング。
つまり、
現実のAさんを
実在のAさんと私の二人が
コーチングしている。
実在のAさんとの
協業作業なのです。
しかしこれは
私だけの特有の力では
ありません。
こういったコミュニケーションを
すべての人が
本当は取れるのです。
それが私達人間が
もともと持っている
コミュニケーション力の本領です。
その本領を
取り戻していただくことが
私のあらゆるサポートの柱の一つに
なっています。
これは
1対1のコミュニケーションだけでなく、
チームによるミーティングでも
同様です。
私がある組織の
チームコーチングに入ると、
そこにもし10名の人がいたとしたら、
10名の皆さんの実在とも
会話をしながら進めます。
つまりそこには
20名の皆さんがいるような
ものです。
そして、
実在の10名と私が、
現実の10名をチームコーチング
するのです。
ですから、
話をもどすと
沈黙。・・・
これがいかに
大切なことか。
皆さんが、沈黙したその瞬間に
いかに皆さんの「実在」が
活性化するかを
私はいつも実感しています。
実在の活性化を
現実の活性化に
つなげる。
私は、こういった
実在コミュニケーションを
駆使できるコーチが
増えるといいなぁと
願っています。
そしてできれば、
企業の経営者や
組織のリーダーとなる人が
実在コミュニケーションできると
いいなぁ、と
願っています。
いえ、本当は
すべての人に
早く、実在コミュニケーション力を
取り戻してほしいのです。
そのために私にできることは
何か?
それが私の今後の活動の
基本テーマです。
つづく
今、目の前に
人がいます。
その人と
向かい合っています。
その人は、
あなたですか?
あなた自身ですか?
そう問われた時、
顕在意識のレベルではもちろん
いやいやいや、
目の前にいるその人は
自分とは別の人です、
と思うはずですが、
あくまでそれは
現象レベルの話です。
あなたの実在(心の中の世界)では
あなたは
どう感じているでしょうか?
やはり心の中でも
この人は私とは別の人だ、
と感じているでしょうか。
それとも、
この人は私自身だ、
と感じているでしょうか。
どちらが良いとか、
どちらが素晴らしいか、
ということではなく、
恐らく、
両方を感じている人が
多いのではないかな?
実は、
それが「実在」なのです。
「実在」の世界には
階層があります。
私はそれを
「次元」
と呼んでいます。
しかもそれを
数値で表しています。
次元が高まれば高まるほど、
「すべては一つである」
という実感が強まります。
「すべては私自身である」
という実感が当たり前と
なります。
次元が低くなればなるほど、
すべてに対して
分離感を得ます。
別物である、という感覚ですね。
私達の心の中の世界では
そういった様々な次元が
同時に存在しています。
高い次元から低い次元まで
様々な次元の自分を
持ち合わせているのが
私達人間です。
・・・・・・
目を瞑り、
空をイメージ
してみてください。
雲一つない
濃い青空です。
その青空の中に
漂っている自分を
イメージしてみてください。
現実では
あり得ませんが、
上も下も右も左も前も後ろも
すべてが
真っ青。
真っ青な空間の中に
一人でポツンと
漂っています。
そのまましばらくの時間
ジーッとしていて
ください。
何も考えず、
ただ、意識は
青空の「青」に
向け続けます。
それを続けていますと、
自分と青空の
区別がなくなって
きます。
自分は青空であり、
青空が自分であり。
自分はここにいるのに
ここではないどこかにも
いる。
自分は個であり、
自分は全体でもある。
自分は一点であり、
自分は「すべて」でもある。
すると、
青空である自分から
体を持っている自分が
観えるかもしれません。
自分の体に入ったり、
抜け出たり、
上から自分の体を観たり、
下から観たり、
後ろから観たり、
またもどったり。
あらゆる場所に
自分の意識を置けるように
なります。
それは
「自由」
です。
それは
「開放」
です。
これを充分に楽しんだら、
目を開けましょう。
すると目の前には
「現実」がありますね。
それが
「現象」です。
すべての現実(現象)を
ありありと観察してみて
ください。
いかがですか?
ちょっといつもとは違った
感覚で
自分の脳に
飛び込んできませんか?
「今ここ」が。
この感覚で
人と向き合うと、
結構、
面白いですよ。
・・・・・・
目の前にいる
その人は
「現象」です。
それは、
自分自身の反映でも
あります。
その人が
自分に対して、
どのような雰囲気で
どのような一言を
投げてくるのか?
そこに
自分の生き方のすべてが
映し出されています。
私達はいつも、
自分自身の反映と
向かい合いながら
生きているのです。
最近、
目の前にいるその人の
お顔は
幸せそうですか?
自由そうですか?
それとも、
苦しそうですか?
窮屈そうですか?
もし、
苦しそうであり、
窮屈そうであるならば、
あなたには、
何か手放すべきものが
あるはずです。
手放すべきものを
手放していないからこそ、
目の前の人が
苦しむのです。
実在のあなたは
(心の中のあなたは)
すでにそれを
手放しているはずです。
次は
現実のあなたです。
現実のあなたが、
現実の何かを
手放すのです。
つまりは、
行動に移すのです。
行動に移すことで初めて
「手放す」は
完了できます。
早く手放して、
次に進みましょう。
つづく
「自由」と「手放す」
というのは、
ある意味、
同義語かもしれません。
もちろん
イコールではありません。
しかし、
本当に自由な人には
執着がありません。
手放すべきものを
手放すべきタイミングで
すぐに手放すことが
できます。
逆に、
そういう人は、
何を手放してはならないか?
について
とても冷静です。
手放すべきものと
手放してはならないものを
常に落ち着いて判断し、
その通りに実行することが
できます。
そういう人は概して、
とてもあたたかい雰囲気を
持っています。
そして、いい意味で
無邪気です。
一緒にいて、
癒されます。
なぜそうなれるか?と
言いますと、
そういった人は
実在レベルでは
すべてに満たされている
からです。
実在レベルでは
すべては一つである
という感覚が
大きいのです。
現象レベルで
何かを手放しても、
それはただ距離を離すという
だけのことで、
実在レベルでは
一つであるし、もしくは
共に在るのです。
ということを
感覚としてよくわかって
いるのです。
むしろ、
距離を調整することこそが
実在レベルでのあらゆるものの
存在感を
より高め合うことができる
ということも
よくわかっています。
「もうあなたと会うことは
やめにします」
「もうあなたと一緒に
仕事をすることはやめます」
「もう離れて暮らしましょう」
・・・というようなことを
言いながらも、
それをすることで
お互いのつながりや存在や
そして愛が
さらに深くなることを
知っているのです。
・・・・・・
私達が手放せるものの中で、
ある意味
最大のものは、
「人生」
かもしれません。
「人生を手放す」
もちろんそれは
自殺ということでは
ありません。
自分の人生を一度、
完全に手放して
しまうのです。
まずは
実在レベルで。
つまりは、
心の中で。
私は私の人生を
完全に手放せたな。
・・・と100%思えることで
初めて観えてくることが
あります。
例えば、
自分は自分の人生に
いかに執着していたか?
とか。
実は私はこれまで
何度もこれを
しています。
私の場合
そこで発見したのは、
人生の願いやビジョン、
そして、
使命に対して
依存している自分自身でした。
自分の真本音に
依存している自分であり、
自分の真本音に
執着している自分
でした。
もうその時点で
真本音
ではなくなってるんですけどね。
もちろん私達は
人間ですから、
執着があるのは当たり前です。
執着をゼロにすることは
難しいでしょう。
しかし、
執着が執着であることを
知ることが大事であり、
それが執着であるという
自覚のないまま進むことは
できれば避けたいですね。
・・・・・・
今、あなたにとって
最も大事だと思える人を
一人選んでください。
その人を
手放してみてください。
もちろん、
心の中だけで結構です。
でも、
完全に手放してみて
ください。
できます?
できないですよね。
そりゃ簡単には
いきません。
でも、
「手放せた!」
と確信できるまで
がんばって
やってみてください。
もちろん
心の中だけです。
するとそれが
ゼロリセットとなり、
その人との
新たな関係がスタート
するかもしれません。
その人との関係において
これまで思いもよらなかった
発想が
浮上するかもしれません。
同じように、
今の自分の仕事に
対しても
心の中で完全に
手放してみてください。
何をどう
感じますか?
どうしてもそれは
手放せない、
ということであれば、
それはまず間違いなく
執着です。
本当は私達は
自分にとって
真に大事なものであればあるほど
手放すことができるのです。
しかしもちろん、
その執着を無理に取り払う
必要はありません。
でも、
その執着がどのようなものかを
しっかり観察し、
自覚することは大事です。
その執着が
あなたの人生の足を
様々な場面で
引っ張っているかも
しれませんから。
以上は、
現実を本当に動かすわけでは
ありませんので、
「遊び」の範疇です。
でも、
「遊び」だからこそ得られる
発見もあります。
「遊び」だからこそ
一度、
真剣にやってみることを
お勧めします。
つづく
人と人が会った時、
そこで何が
起きているでしょうか?
例えば誰かとコラボで
仕事をしようとした場合、
初めての会合で
何が起きるでしょうか?
私はいつもそこで
「火花」
を観ます。
もちろんそれは
現象(現実)レベルの話
ではなく、
実在レベルの話です。
「火花」は
大きければ大きいほど
私は、いいなぁ
と思います。
火花とは、
ぶつかり合いによって
発生します。
そこにいる人達の
人生と人生の
ぶつかり合いです。
自分の人生のハンドルを
自分でしっかり握ってきた人
であればあるほど、
ぶつかり合いは
激しくなります。
ただしそれは
先ほども申したように
現象(現実)レベルの
ぶつかり合いでは
ありません。
現象レベルのぶつかり合い
とは、
文字通りのぶつかり合い
です。
例えば、
言い合いをしたり、
否定をし合ったり、
どちらが正しいか?
どちらが優れているか?
を競い合ったり。
実在レベルのぶつかり合いは
調和のための
エネルギーの交換であり
循環です。
ぶつかり合えば
ぶつかり合うほど、
その火花は
ますます激しくなり、
エネルギーは
みるみる高まります。
いったん高まって
安定し始めたところで、
またそこに
新たな刺激を入れるのが
私の密かな楽しみです。
すると
さらにそのエネルギー達は
うねり、暴れ、
まるで昇り龍のように
垂直上昇します。
そんな刺激的な
ミーティングが行われると、
私は
いったいこの人達は
どうなるんだろう?
どこまで
行ってしまうんだろう?
と心配になります。笑
この人達は
私の手には負えないな、
どうしよう、
と不安になります。笑
でも私は
知っています。
その心配と不安が
出ることこそが
真の調和への道であり、
本質的なコラボへの
最短距離です。
私はいつも、
物事の展開を
現象と実在の両面セットで
眺めています。
面白いことに、
実在レベルで
手に負えないくらいの
激しさが湧き起こることで
現象レベルでは
非常に穏やかな展開と
なります。
静かで、マイペースで
トツトツと
物事が進みます。
しかし、
場のエネルギーは
とても高く、
恐らく、
真本音度合いの低い人が
その場に来たら、
目眩を起こすかもしれません。
・・・・・・
私はこれから
そんなコラボを
どんどん展開していきたいと
考えています。
幸い今、
私の周りには
私自身がクラクラと
目眩のしそうな人達ばかりが
いらっしゃいます。笑
しかし、
それらの人達は、
皆、自律はしていますが、
まだ本当の意味での
調和に至っていません。
これまでの私のステージが
自律した人との出会い
のステージだったとすれば、
これからは、
それらの人達と
真の調和を生み出していく
ステージだと
思っています。
そしてそれは
現象レベルにおいて
意図的に起こすものではなく、
すべてを実在レベルの
エネルギーのうねりに
委ねてしまうような、
そんな有機的なものに
していきたいです。
シナリオのない
シナリオが
今、始まった感覚です。
・・・・・・
やはり。
テーマは
『自由』
ですね。
結局はこのテーマに
行き着きます。
昨日から
このブログでは
枠を一つ外しましたので、
これからは
「自由」について、
枠を一つ外した状態で
書かせていただきたいなと
思っています。
つづく
節目、というものが
私達の人生には
いくつもありますね。
年の変わる年末年始は
代表的な節目ですが、
会社で言えば、
期が変わる節目とか、
個人で言えば、
誕生日とか、
結婚記念日とか。
様々な節目があり、
その節目ごとに
私達は何かしら
気持ちを新たにしています。
それらは
現象レベルの節目
です。
それとはまったく別として
実在レベルの節目
というものもあります。
実在レベルの節目
というのは
現象レベルのように
何月何日と日付が
決まっているわけでは
ありません。
不定期にその節目は
訪れます。
実は。
4月18日から19日にかけて、
ここに一つの
節目がありました、
実在レベルでは。
・・・・・・
「実在」とは、
私達の心の中の世界
です。
私達の心は
宇宙のように広く
そして深いです。
そして、
すべての人の心は
つながっています。
集合無意識、という
言葉がありますが、
私達は無意識下で
つながっています。
しかもそのつながりの
深さには
階層があります。
表面的なつながりから
深〜いつながりまで。
その奥の奥の奥まで行けば、
私達は「一つ」となります。
「一点」に集約されます。
その「一点」とは
「一点」ではあるのですが、
「無限」です。
そこには「すべて」が
存在しています。
何もない状態を
「無」と言いますが、
その真逆で、
すべてが存在している状態
です。
それを
「空」(くう)
と言います。
その、「空」である中心の一点
であり
無限であるものを
アメリカでは「Source(ソース)」と
呼んでいます。
日本では
『源』(みなもと)
と訳されているようです。
名前のごとく
これがすべての源である
と捉えられているのですが、
実は、
本当は、そうではありません。
「源」のさらにその奥にも
さらなる「一点」が
あるのですが、
それについてはまだ
ここでは言及しません。
とにかく私達の心は
深いです。
そして、
すべてがつながっています。
その心の中に実在している
ものを私は
『実在』
と呼んでいます。
心の中に実在しているもの
という言い方をすると、
それは
「イメージのことか?」
と思われそうですが、
そうではありません。
イメージとは
単なる幻に過ぎません。
言葉は悪いですが、
妄想と同じです。
「実在」は
妄想ではありません。
イメージでもありません。
本当に実在しているものです。
心の中の世界。
すべてとつながっている
世界。
それは
『実在の世界』
と言ってよいでしょう。
実在の世界において
実在しているものが
心の外の世界に
反映されます。
つまり、
私達のいるこの現実世界に
反映されます。
それを
『現象』
と言います。
この世にある
あらゆるものは
「現象」です。
それは、
「実在」の反映です。
「実在」がなければ
決して生まれないものが
「現象」です。
「実在」から
「現象」は生まれます。
つまり、
心の中にあるものが、
現実化するのです。
心理学の世界で
よく喩えられるのですが、
実在とは、映画のフィルムであり、
現象とは、フィルムによって
映し出された映像
のようなものです。
・・・・・・
さて、話を
戻しましょう。
そんな実在の世界において
4月18日と19日の境目が
一つの節目でした。
どんな節目かと言いますと、
一言で表現すれば、
『手放す期限』
です。
私達は、
人生において
何かを手放さなければ
先に進めない
という法則のもとに
生きています。
真本音で
手放そうと思っていたものを
きちんと
手放せたかどうか?
ということは逆に、
これは手放してはならない
と真本音で決めているものを
ちゃんと大事に抱いて
いるかどうか?
そのチェックを
自分自身がする節目
だったのです。
あくまで
自分自身のチェックです。
他の誰かが
するわけでは
ありません。
自分の真本音が
自分をチェックするのです。
チェックの結果
真本音が満足すれば
次のステージに
その人は進みます。
自らの意志でもって。
チェックの結果、
真本音が
これはまだまだダメだな
と判断すれば、
次のステージには行かず、
もう一度、同じステージに
戻ります。
もしくは、
もっとずっと前のステージから
やり直しをします。
もちろん、
これも自らの意志で。
その分かれ道が
4月18日と19日の
節目だったのです。
ダメだったな
という人も
落胆する必要はありません。
ちゃんとやり直しを
すればいいだけのこと。
しかし恐らく
その人はかなりの
後悔をするでしょう。
その、後悔こそが
大事です。
後悔するからこそ
進化があります。
人の人生には
やり直しが効きます。
自分で自分に対して
不合格を出しても、
やり直しをすれば
よいのです。
自分で自分に
合格を出せた人は
本当に
よかったですね!
おめでとう!
とお伝えしたいです。
その人達は
次のステージへ出発です。
そこには
これまでに経験したことのない
新たな冒険が
待っています。
それは
ドキドキワクワクする
冒険です。
つづく
私達の人生は
答えのわからないこと
だらけです。
どうすればよいのか?
がまったくわからない。
方法がまったく
思いつかない。
そんなこと
だらけです。
ですから私達は
ついつい
答えのわかる範疇に
留まろうとしてしまいます。
自分が把握できる
世界の中でのみ
生きようとしてしまいます。
自分が見ることのできる
視界の中に
い続けようとしてしまいます。
それこそが
安心であり
安定であると。
しかし本当は、
そういった生き方をし始めることで
私達は
安心と安定を失います。
なぜなら
自分の把握できる視界を
超えていくこと、
今の自分では
「わからない」世界に
飛び出していくこと、
それこそが
私達の本能が望んでいる
ことだからです。
そのための存在が
私達人間だからです。
『進化』
・・・これが、
私達人間の本質です。
進化を失ったとき、
私達の存在意義も
失われます。
つまり、
自分は生きている意味がない
と、
心の奥底で私達は
感じてしまうのです、
進化から逃げることで。
「進化することは怖い」
と言う人がいます。
「進むことが怖い」
と。
よく言う喩えですが、
私達は自転車と同じように、
進むことで安定し
進むことで安心できるのです。
止まってしまうと
途端に不安定になり、
あらゆることにすぐに
恐れを抱くようになります。
それが人間の
性であり
宿命です。
なんて疲れる宿命なんだ!
と思わないでください。
進むことで
疲れは癒されるのです。
進むことで
とても楽になるのです。
そのように創られているのが
私達なのです。
答えがわからない?
方法がわからない?
・・・それこそが
私達の進むべき方向です。
いえ、
進みたい、方向です。
その道を行くことで
私達は
真の安寧を得ます。
・・・・・・
あなたはどれだけ
日々、
人と向き合っていますか?
「向き合う」とは
意識を完全に相手に
向けることを言います。
相手ではなく、
自分の意識や自分の解釈に
意識を向けながら
人と関わるのは
「向き合う」という状態では
ありません。
「向き合う」とはある意味、
目の前の人に
完全に委ねるということでも
あります。
自分がその場を
引っ張るのでもありません。
相手に委ねるのです。
そのためには、
相手を信じるしか
ありません。
「相手を信じる」とは
相手の真本音を信じる
ということです。
信じる、
とは意志です。
信じられるかどうか?
ではありません。
信じようと
するかどうか?
それだけで
決まります。
私はこの人の
真本音を
完全に信じよう。
この人の
真本音に私のすべてを
委ねてしまおう。
その覚悟を持って
その人に
全意識を向けていきます。
するとそこで初めて
私は私の枠を超えた
私になれます。
人と向き合うことで
自分の枠を超える。
・・・これは
私達すべての人間が
持っている
願いの一つです。
その願いに素直に
人と関わり続ける。
私は今のお仕事を通じて
それをし続けることが
できました。
そういった関わり方を
私はすべての皆さんに
お勧めします。
そのような関わり方、
向き合い方を
毎日のようにし続ける人は、
必ず
「真実」を知ることができます。
宇宙の真実
です。
なぜ、この世が
できているのか?
なぜ、この世が
生まれたのか?
私達は
なぜ、ここにいるのか?
私達は皆、
何を目指しているのか?
人と宇宙
(実は、人と宇宙はイコール
ですが)
に関する真実を
実感できるようになります。
すべての真実は
「向き合っているその瞬間」
にあります。
そこにすべての
答えがあるのです。
このブログも
そろそろ
一つの枠を超えようかなと
思っています。
実は、
こう見えて、
かなり私は自分を制御しながら
このブログを
書き続けてきました。
もちろん
すべての制御を
取り去ることはしません。
しかし、
そろそろ
一つだけ、制御を
取り去ろうかな。
ちょいと勇気が
要りますが、
そうすることにします。
なぜならこのブログは
いつも読んでくださっている
皆さんと向き合いながら
書かせていただいて
いるのですから。
つづく
自分のことしか
考えない人は、
自分が今ここにいることに対して、
いったいどれだけ周りから
様々な力をいただいているか?
ということを
まったく気づけないままに
生きることになります。
自分のことを
わかっているのは、
自分だけ。
誰も自分のことを
理解してくれない。
理解しようとも
してくれない。
ひょっとするとそれは
事実かも知れません。
しかしその事実を
創り出しているのは
自分自身であるという
事実もあり、
もしそこに本当に気づけたら
その人はもう8割くらいは
そこから抜け出せたと
言えるでしょう。
自分の孤独を
創り出していたのは、
実は自分自身であった。
そして、
自分の現実を
創り出していたのは、
実は自分自身であった。
この単純な事実を
もしほとんどの人が
腑に落とすことができたら、
それだけで
世の中は変わると
思うのです。
ところが。
ご承知の通り、
そう簡単にはいかないのが
現実でもあります。
ここで、
ちょっと視点を
変えて。・・・
「あなたは今、
どこにいますか?」
と問われて、
あなたは何と
答えますか?
時たまですが、
私は突然クライアントさんに
そのように問うことが
あります。
多くの人は
「ここにいます」
と答えます。
でも本当に
そうでしょうか?
次の問いを
真摯に受け取って
みてください。
その上で、
自然に浮かぶ答えを
自分の中から
聴いてみてください。
「あなたは今、
本当に、ここにいますか?」
どうでしょう?
どんな答えが
浮上しますか?
やはり、
「ここにいます」
という答えですか?
もし
「ここにいます」
という答えでしたら、
次の問いを
自分に投げてください。
「本当に本当に
ここにいますか?」
そして、
「本当は
どこにいますか?」
と。
なんでこんなことを
書くかと言いますと、
今、「ここにいる」人が
極度に減っているからです。
これは
ここ2〜3週間の
傾向です。
私の印象では、
ほぼ、すべての人が
どこかに行ってしまっている。
ここに、
心と体はあるけれど、
魂が
どっかに行ってしまっている
のです。
もう一度、
このように問うて
ください。
「今、私は本当は
どこにいるのだろうか?
どうして、
そこにいるのだろうか?」
ここにいないことを
決して悪いことだと
思わないでください。
意味があって
あえて、
ここにいないのだと
思ってください。
どこかに行っていて
いいんだよ。
今は、そんな
時期なんだよ。
必要があって
そうしてるんだよ。
という気持ちで
自分自身に
問うてください。
「今、私は
どこにいるの?
何のために
そこにいるの?」
そして
さらに次のように
問うてください。
「何が完了したら、
ここに戻って来れるの?」
自分がここにいない、
真の理由を
できるだけ明確に
してください。
それをしなければ、
あなたはだんだんと
孤独になります。
そして冒頭に書いた通り、
自分のことしか考えない
という状態に
入ります、
今、ここにおいては。
私達人間は
「今、ここにいて
今、ここを生きる」
ことができて初めて、
周りとのつながりを
実感できるように
できています。
今、ここにいないということは
本来の自分を
見失うことに
直結します。
しかし、
今、多くの人が、
わざと
「今、ここにいない」
という状態を創り出して
います。
理由は
今の私にはわかりませんが、
恐らく、
そのうちに、近いうちに
わかるでしょう。
ただ、私が
皆さんにお伝えしたいことは、
今自分は、ここにいないのだ
という事実を知り、
そして、そのことに
大いなる意味があることを知り、
そういった状態にある自分を
許し、
大らかな眼差しで
自分を見つめてあげてほしい
ということです。
皆さんは今、
今ここから離れることで
何かを得ようとしています。
早くそれが
得られればいいなと
願います。
つづく
豪雪の中、
立っている私が
いた。
雪はどんどん降り積もり、
私の全身は雪の中に
埋もれようと
していた。
抗うことを
まったくせず、
私は、自分が
閉ざされていくままに
していた。
このままいったら
私は死んでしまう
のではないか。
やり残したこと
いっぱいあるなぁ。
そう思いながらも
だんだんと
意識が遠のいて
いく。
うわぁ、
これじゃホントに
死んでしまうよ。・・・
・・・ハッと気がつくと
私は布団の中。
どうやら
夢だったようだ。
いや、
どう考えても
今のは夢ではない。
夢であるもんか。
たった今、
本当に経験したような
生々しさが
ある。
私は、私の人生の終わりを
本当に経験
したのではないか?
そう心の中で
つぶやくと、
まるでそのつぶやきに
返事をするかのように、
そうだよ、
本当に経験したんだよ、
と、また
私自身の心が
つぶやいた。
いったい、私とは
何なのだろうか?
私のこの人生とは
何のための
ものだろうか?
そんな問いが
浮かびながらも、
また私は
ウトウトし始めた。
ふと気がつくと、
私は暗闇の中。
何も見えない。
しかし、
私の周りに
複数の人達の気配が。
誰だ?
と思って周りに
意識を向けると、
姿は見えないけれども
どうやら
私の仲間のようだ。
なんだ、君らか・・・。
それは、
いつも当たり前のように
一緒にいる
私のファミリーのような
仲間達。
私は彼らと共に、
暗闇の中で
何か一点を見つめていた。
見つめる先に
目をやると、
そこには私自身の
姿があった。
横たわっている
私自身の姿。
その私にはすでに
意識はないようだ。
今、
心臓が止まろうと
しているのが
わかった。
あぁこれは、
私の人生が終わる
瞬間だと
直観した。
心臓の鼓動が
どんどん弱まって
いく。
もうほとんど
止まっている
と言ってもいい。
時々、思い出したかの
ように、
ドクン、と波打つだけ。
あぁもう本当に
私は死ぬんだな、
と、
私を見ている私は
つぶやいた。
すると、
暗闇の中の
仲間の一人が
私に訊いた。
どうでした?
いい人生でした?
私はニッコリと
笑った。
うん。
とっても
いい人生だったよ。
だって、
やり残したことが
一つもない。
さっきはさ、
やり残したこと
たくさんあるな、って
思ったけど、
違ったよ。
私がすべきこと
私が本当にやりたいことは
すべて完了した。
今わかったよ。
完了感が
ハンパない。
なんかさ。
これ以上の人生は
ないんじゃないかな、
と思えるくらいの
満足感だよ。
こういう人生も
あるんだな。
いやぁ、
いい人生だったよ。
すると、
暗闇の中の別の
仲間が
あっ、
もう完全に
止まりそうですよ、
・・・と。
私が見降ろすと、
横たわっている私の
心臓は
確かに最後の
一鼓動を
打とうとしていた。
あと一回、
心臓がドクンと
動いたら、
それで
終わりだ。
それで
この人生は
終わりだ。
あぁ、
本当に良かった。
いい人生
だったなぁ。
私は
私の人生のビジョンを
ちゃんと達成
できたなぁ。
まさか本当に
達成できるとはなぁ。
・・・と、
つぶやいた瞬間に
ハッと
私の意識は
もどった。
私は布団の中に
いた。
なんだ、
また夢か。
いやいやいや、
今のが夢で
あるもんか。
どう考えても
今まさに
経験したことだ。
今のはいつの
経験だ?
と問うた瞬間に
答えが浮かんで
きた。
あぁそうか。
30年後だ。
私は今、
ちょうど30年後の
自分を経験
したんだ。
ということはやっぱり
夢ではなく、
今のは実在だな。
そう言えば私は
自分のビジョンが達成
できたと、
つぶやいていたな。
30年後のビジョン、
とは何だろう?
・・・と問うた瞬間に
その答えが
浮かんだ。
あぁそうか。
これが私の
ビジョンか。
そうだったのか。
私はこのビジョンを
実現するために
生まれてきたんだ。
これが私の
人生の
目的か。
そう思った瞬間に、
これまでの私の人生の
道のりのすべてが
腑に落ちた。
なるほど、
私のこれまでの人生は
すべて
このビジョン実現の
ためのものだったんだ。
これからの人生の
すべても
きっとそうだ。
な〜んだ、
そうだったのか。
私は、
これまで
味わったことがないくらいの
スッキリ感を
味わった。
・・・・・・
これが、
私が
自分自身の人生のビジョン
を初めて認識できた
瞬間です。
私はそれを
「30年ビジョン」
と名づけました。
それから2年が
経ちました。
私は今、ようやく
30年ビジョンに向かって
本格始動
できそうです。
まぁ、
2年経ったので
あと28年ですが。
あと約半月後の
5月1日に
私は一つの法人を
立ち上げます。
ダイレクトに
ビジョンに向かうための
会社です。
名前はもう
そのまんま。
『株式会社真本音』
です。
つづく
私達の真本音は
距離(感)をとても大事にしている
というお話をしました。
(→【人生の展開は距離感で決まる】)
本当に面白いことですが、
例えば、AさんとBさんがいた場合、
距離(感)が
真本音が望むものであれば、
AさんとBさんはお互いに
パワーを与え合い、
パワーの循環を起こします。
が、
距離(感)が
真本音の望むものとズレていた場合、
二人はお互いに
パワーを奪い合う関係になってしまう、
・・・そんなケースが
非常に多いのです。
距離(感)によって
真逆の関係になるのです。
そしてその距離(感)とは、
・実在の距離と
・現象の距離が
あります。
実在の距離を適正なものに
することで、
現象の距離も適正に
なります。
一つ、実際にあった例を
かいつまんで
ご紹介しましょう。
ある会社で、
私はAさんのコーチングを
していました。
Aさんは、
言われました。
「どうしても私はB課長と
上手くいきません。
・・・というより、
B課長と一緒に仕事をしたく
ありません。
こんな子供のようなことを言うのは
ナンセンスだとわかっています。
でも、本当のことを言えば、
B課長と一緒の空気を吸うこと
自体が嫌なのです。
私は会社を辞めようと
思っています。」
そこで私は
Aさんに目を瞑って
いただきました。
そして次のように
問いました。
「Aさん、
B課長のイメージをしてみてください。
B課長のイメージは
どの場所に浮かぶかわかりますか?
その場所を特定してみてください。」
以下、Aさんと私のやりとりです。
Aさん
「B課長は私の正面の前方
3mくらいの場所にいます。」
たけうち
「その距離はAさんにとって
居心地の良い距離ですか?」
Aさん
「いえ、とてもきついです。」
たけうち
「もっと近づけたいですか?
それとももっと遠ざけたいですか?」
Aさん
「もちろん、もっと
遠ざけたいです。」
たけうち
「どれくらいの距離に
遠ざけたいですか?」
Aさん
「・・・。
15mくらいでしょうか。」
たけうち
「本当に15mで良いですか?」
Aさん
「・・・、いえ、もっと
離してしまってもいいですか?」
たけうち
「もちろん良いですよ。」
Aさん
「じゃあ、・・・60mくらい。」
たけうち
「本当に、60mで良いですか?」
Aさん
「えぇ? これ以上離しすぎると
姿が見えなくなってしまいます。
まずくないですか?」
たけうち
「大丈夫ですよ。
Aさんが本当に望む距離は
どれくらいですか?」
Aさん
「できれば、姿はもう見たく
ありません。
2kmくらい離れちゃっても
いいですかね?」
たけうち
「本当に2kmでいいですか?」
Aさん
「ええっ? だってそんなに
離したら、なんか悪いです。」
たけうち
「悪くないですよ。
これは単なるイメージ遊びです。
本当の本当の望みを
言ってみてくださいよ。」
Aさん
「・・・実はですね、本当は
地球から出て行ってほしい
くらいなんです。
・・・僕、ひどいこと言ってますね。」
たけうち
「大丈夫ですよ。
じゃあそれを数字で表すと
どれくらいですか?」
Aさん
「う〜ん・・・。
3000万kmくらいでしょうか。」
たけうち
「おっ、いいですね。
やっとAさんの空気感が安定しましたよ。
では、イメージのB課長を
Aさんから3000万km
離してみてください。」
Aさんはその通りに
イメージをしてみました。
たけうち
「いかがですか?
どんな気持ちになりますか?」
Aさん
「いや、なんか凄く
楽になりました。
体の力が抜ける感じですね。」
たけうち
「じゃあ、Aさん。
いつもB課長を今のように
3000万km離した状態で
いてください。
イメージの中では。
で、あとは実際には
いつもの通りにB課長と
接してみてください。」
それから2週間後、
再びお会いしたコーチングの場で、
Aさんはしみじみと
言われました。
「たけうちさん、驚きです。
B課長のことがそんなに
嫌じゃなくなりました。
むしろ課長のことを
よく観察できるようになりました。
で、自分でも驚いていますが、
先日、課長を誘って
一緒にランチに行ったんですよ。
課長とあんな風に話せたのは
初めてです。」
・・・
この話、あまりに上手く
でき過ぎているように思われそうですが、
実際にあったお話です。
もちろんこの例だけでは
ありません。
このように
イメージの距離を修正することで
イメージの中での調和が起こり、
それが現実の調和に
影響を及ぼすのです。
でも実はこれ、
本当は
「イメージ」ではないのです。
これは
「実在」です。
「実在」を
動かしたのです。
「イメージ」と「実在」とは
本質的に異なるものです。
「イメージ」でこのようなセッションを
しても、
ほぼ効果は出ません。
「実在」で行なうからこそ、
効果が大きく出るのです。
とりあえず今日は
ここまでにします。
つづく
子どもは
永遠に親の保護のもとに
いるわけではありません。
必ず
親から独り立ちする
瞬間が来ます。
親から離れる
時が来ます。
『子が育ちますように』
この祈りは
誰もの心の中に
いえ、
魂の中に必ず
存在するものです。
この祈りに基づいて
生まれるエネルギーと
そのエネルギーに基づいて
生まれるあらゆる行動や
振る舞いのことを
『慈しみ』
と言います。
これについては
実は
私達人間の「本能」の成立にとって
あまりにも重要なものですから、
改めて時間をとって
ゆっくり書かせていただく
つもりです。
慈しみには必ず、
独り立ち、巣立ち、離れ、
そして、別れ
といったものがセットで
ついて来ます。
きちんと別れるべき時に
別れること。
離れるべき時に
手放すこと。
それは
真の慈しみの行為に
他ありません。
あの人のことが嫌いになった、
だから別れる
という単なる感情による
別れとは
それは本質的に異なる
ということは
誰もがわかるでしょう。
感情的な別れ、とは
反応本音による別れ。
慈しみの結果としての別れ、
とは
真本音による別れ。
どちらも寂しく
悲しいものかもしれませんが、
真本音の別れには
根底に必ず不思議な
すがすがしさが
湛えられています。
真本音で生きるということは
別れるべき人と
次々に別れ、
出会うべき人と
次々に出会う
人生となります。
よく言われることですが、
何かを手放すことで
新たな何かが
入ってくるというのは
真実です。
この3次元の世界に
おいては。
つまり、
感情のまま、もしくは
情に流されたまま、
別れるべき人と別れないことで
出会うべき人と
出会えなくなります。
・・・
何でしょう?
こうしてこの文章を
書いていますと、
様々な人達のお顔が
浮かんで来ます。
ほとんどが私の
クライアントさんですが、
今、多くの人達が
人生を次のステージへと
転換されようと
しています。
先日、
ある人が私に
言われました。
「なんか、この同じ体を
持ったまま、
生まれ変わろうとしている
気分です」
と。
まさしく、
そんな感じ。
そんな状態の人が
今、とても増えています。
今が4月だから
ということではない気が
します。
来年の今頃にちょうど
平成から新たな時代に
変わりますが、
その一年前に先んじて
人生の新たな時代に
入ろうとしている人が
多いのかな。
皆さんがちゃんと
新たな時代に入るためには、
ちゃんと
別れるべきと
別れなければなりません。
手放すべきを
手放さなければ
なりません。
中途半端なまま
先に進むことだけは
やめましょう。
先には進まない、
という選択も
もちろんありです。
その場合に、
別れは必要ありません。
行くか、
行かないか。
100か、
ゼロか。
どちらかの
選択にしましょう。
中途半端であること
だけは
やめましょう。
混乱や混沌とは
多くの場合、
中途半端さから
発生するものです。
本当は、
「距離感」についての
具体的な事例を
今回はご紹介しようと
思ったのですが、
あまりにいろんな人の
お顔が浮かぶものですから、
あえてその人達に向けて
今日はメッセージさせて
いただきました。
明日は
具体的な事例を
ご紹介できるかな?
つづく
私達の人生において
大きな転換のきっかけと
なるものに
「出会い」
がありますが、
その一方で、
「別れ」
というものがもたらす
影響も大きいですね。
出会いは概して
嬉しいものですが、
別れは概して
寂しいものですし
大きな悲しみを
伴うこともあります。
そのため結果的に、
「本当は今、
別れなければならないのに、
別れられない」
という現実を
創り出してしまっている
人が多いのが、
今の世の中の一つの傾向です。
実は、
どれだけ素敵な出会いを
重ねてきても、
きちんと別れるべき人と
別れないことで、
真本音度合いを著しく
落としてしまい
人生の不調和が始まって
しまった、
という人を私は
とても多く観てきました。
「別れ」とは
とても大事なものです。
そして
いつ、誰と別れるか?
を
私達は自らの真本音で
決めています。
もちろん
AさんとBさんが別れる場合、
Aさんの真本音が決めている
別れのタイミングと、
Bさんの真本音が決めている
別れのタイミングは
完全に一致します。
そしてその通りに
別れることができた場合、
二人の人生は
新たなステージに進み、
次の出会いと展開が
二人ともに起こり、
二人ともが
さらに真本音度合いの高い
人生を送ることができます。
別れるべき時に
しっかりと
別れましょう。
もし相手が
反応本音のレベルで
「別れたくない」
と言ったとしても、
その「情」に流されずに
しっかりとそれを
断ち切りましょう。
・・・このように書くと
寂しいでしょうか。
悲しいでしょうか。
冷たい人間だと
思われるでしょうか。
「別れる」という言葉と
ほぼ同義語として、
「手放す」
という言葉もあります。
手放すのも
本当に大事なことです。
本当に必要なタイミングで
別れを自ら切り出せる人、
そして
手放すことのできる人は
愛の深い人だなぁ、
と私は思います。
では、
「別れる」とか「手放す」
という行為の
本質とは
何だと思いますか?
それは私は
「距離を離す」
ということだと
捉えています。
「距離」
とか
「距離感」。
実は私達の真本音は
これをとても
大事にしています。
同じAさんとBさんでも
二人の距離や距離感が
真本音で望むものと
ずれていたら、
そこには不調和が
起きてしまうのです。
逆に言えば、
「調和」とは
「距離(感)で決まる」
と言っても
言い過ぎではないでしょう。
特に私達が今いる
この「3次元」という世界は
すべてが分離している
世界です。
分離しているが故に
一つ一つの物事
(その中に当然、「人」が
含まれます)
との距離(感)が
あらゆるものの展開に
影響を与えます。
その距離(感)とは、
心の中の距離(感)と
実際の距離(感)の
両方があり、
その両方を
真本音の望むものと一致させる
ことが「調和」のためには
必須です。
ちょっと
わかりづらいですか?
もう少し詳しく
お話しした方が
良さそうですね。
事例を交えて。
ただ、そのためには
ちょっと文章が長くなりますので、
続きは明日に。
まずは今回は皆さんに
二つの問いを
残しておきます。
単純に
直観でお答えいただくと
よいですね。
以下の問いを
自分自身に向けて
投げてみてください。
「私の人生において、
私はあらゆるものと
適正な距離感を持つことが
できているだろうか?」
そして、
「私が今、もっと
距離を離すべきものとは
何だろうか?」
つづく